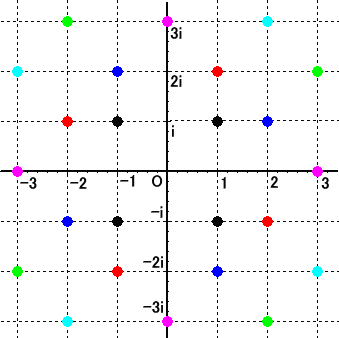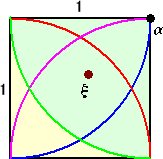1.整数論の基礎知識 
(1) ガウスの整数
中学・高校で、 ・・・、−2、−1、0、1、2、・・・ を整数と言ってきたが、ここでは、有理
整数と言い換え、
複素数 a+b・i (a、b は有理整数 、i は虚数単位)
の形の数を、整数(ガウスの整数)と呼ぶことにする。
この整数は、和・差・積の演算について閉じているが、商については閉じていない。
2つの整数 z 、w (w≠0)について、ある整数 α が存在して、
z=α・w
が成り立つとき、 z は、w の倍数(w は、z の約数)または、z は w で割り切れるという。
w|z とも記される。
例 0=0・w なので、0 は全ての整数の倍数である。
(1+2・i)・(3+4・i)=−5+10・i なので、−5+10・i は、3+4・i の倍数
複素数では、絶対値 |a+b・i|= が大活躍するが、整数論では、
が大活躍するが、整数論では、
N(a+b・i)=(a+b・i)・(a−b・i)=a2+b2
が用いられる。これを、整数 a+b・i のノルム(Norm)という。
z=a+b・i の共役を、 =a−b・i で表せば、 N(z)=z・
=a−b・i で表せば、 N(z)=z・ =|z|2 なので、ノルム
=|z|2 なので、ノルム
は、絶対値とほぼ同じ概念といえる。
ノルムN(z)は、0以上の整数で、N(zw)=N(z)・N(w) 、N(z/w)=N(z)/N(w)
整数論で絶対値を用いない理由は、多分、根号が煩わしいからだろう。(個人的予想!)
根号を使わないので、
整数 z のノルム N(z)は、整数 z の倍数
であることが分かる。
このノルムを用いて、最大公約数、最小公倍数が定義される。
最大公約数 ・・・・・ 公約数のうちで、ノルムが最大のもの
最小公倍数 ・・・・・ 公倍数のうちで、ノルムが最小のもの
例 2 と 2i の最大公約数・最小公倍数を求めよ。
2=(1+i)・(1−i) 、2i =(1+i)2 なので、
最大公約数は、1+i で、最小公倍数は、(1+i)2・(1−i)=2+2・i
ノルムと同様にして、シュプール(Spur)(または、トレース(trace))が定義される。
S(z)=z+
シュプールS(z)は、偶数で、S(z+w)=S(z)+S(w)
例 z=3+2i のノルム N(z)=(3+2i)・(3−2i)=13
シュプール S(z)=(3+2i)+(3−2i)=6
有理整数では、「1」という数が重要であった。有理整数の群としては単位元であったし、数
直線では、数0と数1の間の長さを単位として、他の数の配置を求めたりもした。
また、有理整数 1 は、全ての有理整数の約数という性質も持っていた。ここでは、この性
質に注目して、単数という概念が理解される。
全ての整数の約数となる整数を、単数という。
1=1+0・i も整数なので、明らかに、単数 ε は、1 の約数である。よって、ある整数 δ
が存在して、1=ε・δ が成り立つ。
よって、 N(ε・δ)=N(ε)・N(δ)=N(1)=1 より、 N(ε)=1
したがって、 ε=a+b・i とおくと、 a2+b2=1 なので、
(a , b)=(1 , 0)、(−1 , 0)、(0 , 1)、(0 , −1)
以上から、ガウスの整数における単数は、1、−1、i 、−i の4個であることが分かる。
これらは丁度、ガウス平面において、原点中心、半径 1 の円と各軸との交点である。
有理整数では、素数という概念が重要であった。素因数分解により、有理整数の構造・
性質が明らかとなった。ガウスの整数においても、同様の議論が可能である。そのために、
ガウスの整数における素数を定義しなければならない。
整数 z に対して、単数 1、−1、i、−i および、z、−z、iz、−iz
は、自明な約数で、有理
整数における、1と−1 と同様に因数としては、度外視して考えるものとする。
例 6=1・6 とは普通考えない。 6=2・3 と因数に分解する方が自然であろう。
整数 z に対して、自明でない約数を、真の約数という。
このとき、整数 z が、0でも単数でもなく、かつ、真の約数を持たないとき、素数であると
いう。
例 2 は素数でない。 実際に、2=(1+i)・(1−i) で、真の約数 1+i 、1−i を持つ。
例 3 は素数である。
実際に、3 が素数でないとすると、真の約数 z 、w が存在して、3=z・w と書ける。
このとき、N(3)=N(z)N(w) より、N(z)N(w)=9 である。N(z)、N(w)>1 なので、
N(z)=N(w)=3 となる。ところが、この式を満たす整数 z は存在しない。
もし、z=a+b・i (a、b は有理整数)が存在するとすると、a2+b2=3 とならなければな
らないが、それは不可能。
なぜなら、 a2+b2≡3 (mod 4) において、左辺は、0,1,2 の場合しかないので、
矛盾である。
よって、3 は素数である。
有理整数の世界で素数であったものが、素数だったり、そうでなかったりと、ガウスの整
数の世界は、今までの有理整数の世界とは若干違うようである。そこがまた数学の面白さ
なのだろう。
整数が素数かどうかを判断する公式として、次の定理が知られている。
定理 整数 z のノルム N(z) が素数ならば、整数 z は素数である。
(証明) 整数 z が素数でないとすると、真の約数 α 、β が存在して、z=α・β と書ける。
このとき、N(z)=N(α)N(β) が素数より、N(α) または N(β) の何れかが 1 である。
しかるに、α 、β は、真の約数なので、N(z)、N(w)>1 でなければならない。
これは矛盾である。よって、整数 z は素数である。 (証終)
(注) N(3)=9 が素数でないのに、3が素数であるように、上記の定理の逆は成立しない。
ガウスの整数で、素数といわれるものをいくつか調べておこう。
例 1+i ・・・ N(1+i)=2 は素数より。
1−i は、1−i =(−i)・(1+i) により得られる。
一般に、単数 ε を用いて、z=ε・w と書けるとき、z と w は同伴数であるという。
整除の問題(割り切れる・割り切れない)において、整数を同伴数に置き換えても何ら影響
はないので、同伴数を同一の因数とみなしてもよい。
したがって、2=(1+i)・(1−i)=(−i)・(1+i)2 において、2 という数は、2つの方法で
素因数分解できるように見えるが、この約束により、2 という数は、素数 1+i の2乗に素因
数分解されることが分かる。
a 、b>0 のとき、
a−b・i =(−i)・(b+a・i)、−a+b・i =i・(b+a・i)、−a−b・i =(−1)・(a+b・i)
なので、以下では、 a+b・i (a 、b>0) の形の整数について調べることにする。
例 2+i ・・・ N(2+i)=5 は素数より。
例 3+2・i ・・・ N(3+2・i)=13 は素数より。
3+i は素数でない。実際に、3+i =(1+i)・(2−i)より。
例 4+i ・・・ N(4+i)=17 は素数より。
4+2・i は素数でない。実際に、4+2・i =2・(2+i)より。
4+3・i は素数でない。実際に、4+3・i =(1+2・i)・(2−i)より。
例 5+2・i ・・・ N(5+2・i)=29 は素数より。
5+i は素数でない。実際に、5+i =(1+i)・(3−2・i)より。
5+3・i は素数でない。実際に、5+3・i =(1+i)・(4−i)より。
例 5+4・i ・・・ N(5+4・i)=41 は素数より。
素数の分布の様子を図示すれば下図のようになる。(同色は、同伴数)
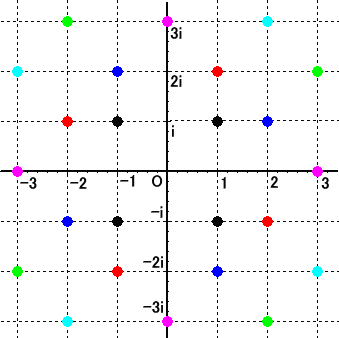
(参考) 西山 豊 著 人とヒトデとサッカーボール (三省堂)の197頁に、この素数の分布
の様子を表した図が掲載されている。上図では分かりにくいが、きれいな幾何学模様で、
1988年ハンガリーで開催されたICME(国際数学教育研究会)で、イギリスのグループ
が素数の分布を表す模様のスカーフを展示したそうである。
整数 z に対して、素数 α 、β 、・・・ があって、 z=α×β×・・・ と積の形にかけるとき、
整数 z は、素因数に分解されるという。
ここで、素因数は有限個しかない。
実際に、整数 N(α)、N(β)、・・・ は、1 より大きい整数で、N(z) は有限の値より明らか。
今までの話から、整数 z がいくつかの素因数に必ず分解できるということは理解できるだ
ろう。しかし、素因数分解において、大切なことは、その分解の一意性にある。もし、一意性
が成立すれば、有理整数における性質が、ガウスの整数においても同様に成り立つことに
なる。
一意性を証明するためには、いくつかの準備が必要となる。まずは、整除の定理から。
定理 任意の整数 z 、w (w≠0) に対して、
z = w・α+β ( N(β)<N(w) ) を満たす整数 α 、β が存在する。
(証明) 任意の整数 z 、w (w≠0) に対して、複素数 ξ=z/w が定義される。
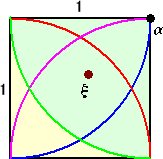 |
ガウス平面(複素数平面)において、左図からも明らかなよう
に、ある整数 α が存在して、 N(ξ−α)<1 とできる。
そこで、 β=z−w・α とおくと、β は整数で、
N(β)=N(z−w・α)=N(w・(ξ−α))
=N(w)・N(ξ−α)<N(w)
|
| 以上から、z = w・α+β (N(β)<N(w) ) を満たす整数 α 、β が存在する。 (証終) |
この定理により、ガウスの整数においても、ユークリッドの互除法を行うことができる。
任意の整数 z 、w (w≠0) に対して、z = w・α+β ( N(β)<N(w) )を満たす整数
α 、β が存在する。 もし、β = 0 なら、z は、w で割り切れる。
β ≠ 0 のとき、w = β・γ’+γ (N(γ)<N(β) )を満たす整数 γ 、γ’ が存在する。
このような操作を続けると、ノルムは、0 以上の整数なので、結局最後は、δ = ε・ζ’
を満たす整数 ζ’ が存在する。(つまり、ζ=0 で最後は割り切れる!)
このとき、ε は、整数 z 、w の公約数である。逆に、整数 z 、w の公約数は、ε の約数
でもあるので、ε は、整数 z 、w の最大公約数であるといえる。
通常、最大公約数 ε は、整数 z 、w を用いて、 ε = ( z , w ) と書かれる。
以上の話を整理すると、有理整数の場合と同様に、次の定理が成り立つ。
定理 任意の整数 z 、w (w≠0) に対して、 α・z + β・w = ( z ,
w )
を満たす整数 α 、β が存在する。
(証明) ユークリッドの互除法から明らか。 (証終)
例 2つの整数 7+4・i 、9+2・i の最大公約数を求めてみよう。
9+2・i = (7+4・i)・1+2−2・i 、7+4・i = (2−2・i)・(1+3・i)−1
2−2・i = (−1)・(−2+2・i)
よって、最大公約数は、−1 である。
このように、単数が最大公約数であるとき、2つの整数は、互いに素であるという。
例 2つの整数 3−i 、4−3・i の最大公約数を求めてみよう。
4−3・i = (3−i)・1+1−2・i 、3−i = (1−2・i)・(1+i)
よって、最大公約数は、1−2・i である。
#このとき、1・[ 4−3・i ]+(−1)・[ 3−i ] = 1−2・i が成り立つ。
いよいよ、素因数分解の一意性を証明する準備ができたようだ。
補題 整数 z 、w が互いに素であるとき、
z・α が w で割り切れれば、α は、w で割り切れる。
(証明) 整数 z 、w が互いに素なので、x・z + y・w = ε (ε は単数) となる整数
x 、y が存在する。このとき、ε・α = x・z・α + y・w・α は、w で割り切れる。
すなわち、α は、w で割り切れる。 (証終)
定理 任意の整数 z は、一意に素因数分解される。
(証明) 整数 z が、2通りに素因数分解されるものと仮定する。
z = α1×α2× ・・・=β1×β2× ・・・
このとき、補題により、単数 ε1 、ε2 、・・・ として、
α1×α2× ・・・ = (ε1×ε2×・・・)・(β1×β2× ・・・)
と書ける。
よって、2通りの素因数分解は、単数の差しかないので、一意であるとしてよい。 (証終)
上記で、ガウスの整数における素数の例をいくつか挙げたが、一般に、素数は、どのよう
な形をしているのだろうか?これも、大いに興味のあるところである。
以下で、ガウスの整数における素数と区別するために、有理整数における素数を、有理
素数と呼ぶことにする。
いま、整数 z を素数として、その性質を見ていこう。
z で割り切れる正の有理整数のうちで最小のものを、p とする。このような
p は必ず存在
する。(例えば、N(z)は、z で割り切れる。)
このとき、 p は、有理素数である。
実際に、 z は素数で単数ではないから、p > 1 で、p が有理素数でないとすると、
p = α・β ( p>α>1 、p>β>1 ) となる有理整数 α 、β が存在し、
α または β は、z で割り切れる。
これは、p の最小性に矛盾する。 よって、 p は、有理素数である。
したがって、素数 z は、有理素数 p の約数となる。そこで、 p = z・γ とおける。
このとき、 N(p)=N(z)・N(γ) で、N(p)=p2 なので、N(z)=p または N(z)=p2
となる。 N(z)=p のとき、 z=a+b・i とおくと、 a2+b2=p より、 p=z・
N(z)=p2 のとき、 N(γ)=1 で、γ は単数で、z は、p と同伴数となる。
このとき、p は、ガウスの整数としても素数となり、N(z)=p のときのような p の分解は
不可能である。
以上から、
素数 z=a+b・i と有理素数 p について、
N(z)=p のとき、 p は素数でなく、 p=z =a2+b2 と分解される。(→参考)
=a2+b2 と分解される。(→参考)
N(z)=p2 のとき、 p は素数で、a2+b2=p を満たす a 、b は存在しない。
したがって、有理素数 p について、方程式 x2+y2=p の解を吟味することにより、素
数が求められる。
例 p=2 のとき、 方程式 x2+y2 = 2 の解は、
( x , y )=( 1 , 1 )( 1 , −1 )( −1 , 1 )( −1 , −1 )
よって、 p=2 は素数でなく、素数 z は、1+i 、1−i 、−1+i 、−1−i となる。
このうち、1−i 、−1+i 、−1−i は、すべて 1+i の同伴数である。
実際に、 1−i = (−i)・(1+i)、−1+i = i ・(1+i)、−1−i = (−1)・(1+i)
方程式 x2+y2 = p (p≠2)の解があるとする。 p は、奇数なので、x または y のうち
一方は偶数、他方は奇数である。このとき、p は、4で割って、1余る数である。
このことは、4で割って、3余る有理素数 p に対して、a2+b2=p を満たす a、b が存在
しないことを意味し、
4で割って3余る有理素数 p は、ガウスの整数としても素数
となる。
例 有理素数 3 は、素数である。(→ 参考)
例 有理素数 7 は、素数である。
例 有理素数 11 は、素数である。
p が、4で割って、1余る数のとき、方程式 x2+y2 = p は、どのような解を持つのだろう
か?(→ Legendre の記号、指数等について既に理解されている方は、こちらへジャンプ)
ここで、整数論では大切な記号 Legendre の記号を復習しておこう。
例 方程式 X2≡1 (mod 3) は、X=3n±1 (n は整数)という形の解を持つが、
方程式 X2≡2 (mod 3) は、決して解を持たない。
一般に、p を2以外の素数として、方程式 X2≡a (mod p) が
解を持つとき、 a を p の平方剰余
解を持たないとき、a を p の平方非剰余
という。
例 3で割った余りは、0、1、2 であるが、その余りを平方したものを3で割った余りは、0、
1 の場合しか起こらない。
このとき、0 と 1 は、3 の平方剰余となり、2 は、3 の平方非剰余となる。
例 7で割った余りは、0、1、2、3、4、5、6 であるが、その余りを平方したものを7で割った
余りは、0、1、2、4 の場合しか起こらない。
このとき、0 と 1 と 2 と 4 は、7 の平方剰余となり、3 と 5 と 6 は、7 の平方非剰余と
なる。
02≡0 (mod 7) 、12≡62≡1 (mod 7) 、32≡42≡2 (mod 7)、
22≡52≡4 (mod 7)
a が、p で割り切れないとき、a が平方剰余であるか、平方非剰余であるかを次のような
記号を使って表す。
| 平方剰余のときは、 |
 |
=1 |
|
平方非剰余のときは、 |
 |
=−1 |
この記号を、Legendre の記号という。
紙面の都合上、以下では、Legendre の記号を、(a/p) で表すことにする。
例 (1/3)=1 、(2/3)=−1
GAI さんからのコメントです。(平成24年3月8日付け)
平方剰余の法則と言って、なにやら直感では何を言おうとしているのか掴み難い式で表現
されているのを見ることがあり、よく分からないと言うのが実感です。ある本で、この法則を次
のような表現で解説してある文章があったので、メモしていました。このことと、なにか関係が
ありますか?
表現:
pとqが奇素数で、どちらでも 4k-1 という形でなければ、q≡y2 (mod p) が解を持つと
きに限って、方程式 p≡x2 (mod p) は解を持つ。
また、pとqのどちらかが、4k-1という形であれば、どちらか一方の方程式は解を持ち、もう
一方の方程式は解を持たない。
これでもややこしい解説ではあるのですが、ただ数式で書いてあるよりはイメージが取り易
い気はします。平方剰余の解釈として、これでいいのでしょうか?
空舟さんからのコメントです。(平成24年3月8日付け)
まさにそれです。個人的には「平方剰余の相互法則」のバニラとチョコレートの解説がすご
く具体的だと思います。
ただし、その表現だとちょっと違いますね。どちらかがバニラ 4N+1 型のとき、解を持つかど
うか一致、両方がチョコレート 4N+3 型の時、不一致 です。
さて、指数という概念を理解するために、フェルマーの定理を確認しておく。
フェルマーの定理 p が有理素数で、a が p とは互いに素な自然数とするとき、
ap−1 ≡ 1 (mod p)
(証明) 2項定理より、 (m+n)p≡mp+np (mod p) は明らかであろう。
これを一般化して、 (m+・・・+n)p≡mp+・・・+np (mod p) が成り立つ。
m=・・・=n=1 (a 個)とすれば、 ap≡a (mod p) である。
ここで、 a は p とは互いに素な自然数なので、 ap−1≡1 (mod p) (証終)
(追記) 平成22年3月22日付け
2010年度入試の大阪大学 後期 理系 で、上記のフェルマーの定理の証明を問う問題
が出題された。
p は素数、r は正の整数とする。以下の問いに答えよ。
(1) x1、x2、・・・、xr についての式 (x1+x2+・・・+xr)p を展開したときの単項式
x1p1x2p2・・・xrpr の係数を求めよ。ここで、p1、p2、・・・、pr は、0または正の整数で、
p1+p2+・・・+pr=p を満たすとする。
(2) x1、x2、・・・、xr が正の整数のとき、(x1+x2+・・・+xr)p−(x1p+x2p+・・・+xrp)
は、p で割り切れることを示せ。
(3) r は、p で割り切れないとする。このとき、 rp-1−1 は、p で割り切れることを示せ。
(コメント) (1)(2)については、多項定理から明らかだろう。上記の証明に倣う形で、小問
(1)(2)が配置されている。したがって、(3)については、上記の証明と同様に、
x1=x2=・・・=xr=1 とすればよい。
フェルマーの定理より、方程式 ax≡1 (mod p)を満たす自然数解が存在するので、
そのうちの最小の自然数解を、e とすると、 p−1 は、e で割り切れる。
さらに、e の最小性から、 a0 、a1 、a2 、・・・、ae−1 は、p を法として合同にはなり
えない。
特に、e=p−1 のとき、 a を p を法としての原始根(または、p の原始根)という。
例 p=7 のとき、
1 に対する e = 1 、2 に対する e = 3 、3 に対する e = 6 、
4 に対する e = 3 、5 に対する e = 6 、6 に対する e = 2
以上から、7の原始根は、2個あり、 3 と 5 である。
ここで、自然数 1、2、3、・・・、n の中で、n と互いに素な数の個数は、φ(n)で表される。
この関数を、オイラーの関数という。
例 φ(1)=1、φ(2)=1、φ(3)=2、φ(4)=2、φ(5)=4、φ(6)=2、φ(7)=6
オイラーの関数について、次の性質が成り立つ。
(1) 有理素数 p に対して、 φ(p)=p−1 特に、φ(pn)=pn−pn−1
(2) a と b が互いに素ならば、 φ(ab)=φ(a)φ(b)
(証明) (1)は、明らかであろう。
(2)は、次のように示される。
a より小さい数で、a と互いに素な数は、φ(a)個あり、その一つを、α とおく。
このとき、 b 個の数 α、α+a、α+2a、・・・、α+(b−1)a を考える。
これらは、何れも b を法として合同でない。
したがって、ab と互いに素な数は全部で、φ(a)×φ(b)個あるので、φ(ab)=φ(a)φ(b)
が成り立つ。 (証終)
例 φ(2)=2−1=1 、φ(3)=3−1=2 、φ(4)=φ(22)=4−2=2、
φ(6)=φ(2)φ(3)=1×2=2
オイラーの関数 φ(n) を用いると、上記で述べたことは、次のようにも言い換えることが
できる。
p が有理素数で、a が p とは互いに素な自然数とするとき、
aφ(p) ≡ 1 (mod p)
この合同式を満たすφ(n)が最小のものであるとき、a を、p の原始根という。
もし、原始根が存在すれば、それは、φ(p−1)個存在する。
原始根の一つを、g (g≠1)とすれば、1、g、g2、g3、・・・、gp−2 は、互いに合同で
ない p−1 個の数で、いずれも p では割り切れない。
いま、a を p とは互いに素な任意の自然数とするとき、上記のことから、
ge ≡ a (mod p) となる e (0≦ e <p−1 )がただ一つ存在する。このとき、
e = indg(a)
で表し、原始根 g を底とする a の指数(index)という。
(注) ge ≡ a (mod p)、gf ≡ a (mod p)ならば、ge−f ≡ 1 (mod p)
よって、e−f は、p−1で割り切れるので、 e ≡ f (mod p−1)
したがって、上記では、0≦ e <p−1 と限定したが、p−1 を法として考えれば、
a の指数は、一定であるといえる。故に、
a ≡ b (mod p) ⇔ indg(a) ≡ indg(b) (mod p−1)
が成り立つ。
例 7 の原始根の一つ 3 について、3 を底とする指数表を作ってみよう。
30 ≡ 1 (mod 7)、31 ≡ 3 (mod 7)、32 ≡ 2 (mod 7)、
33 ≡ 6 (mod 7)、34 ≡ 4 (mod 7)、35 ≡ 5 (mod 7)
以上から、
| a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 指数 |
0 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
また、上記指数表を眺めていると、
a の値における「 2 かける 3 = 6 」が、指数では、「 2+1 = 6」が対応し、
a の値における「 4 かける 5 = 20 」が、指数では、「 4+5 ≡ 3(mod 6)」が対応
していることが分かる。
このことから、指数には、対数に似た性質があることに気づかされる。すなわち、
p−1 を法として、indg(a×b) ≡ indg(a) + indg(b)
indg(an) ≡ n×indg(a)
証明は、明らかであろう。
上記の指数表を用いて、いろいろ計算してみよう。
(1) 指数計算・・・・・
20 ≡ 6 (mod 7) なので、ind3(20) ≡ ind3(6) = 3 (mod 6)
(2) 指数方程式・・・・・
ind3(X)≡ 2 (mod 6) とすれば、上記表より、ind3(X) ≡ ind3(2) (mod 6)
よって、 X ≡ 2 (mod 7)
(3) 1次方程式・・・・・・
4X ≡ 3 (mod 7) において、ind3(4X) ≡ ind3(3) (mod 6) より、
ind3(4) + ind3(X) ≡ ind3(3) (mod 6)
よって、 4 + ind3(X) ≡ 1 (mod 6) なので、ind3(X) ≡ −3 ≡ 3 (mod 6)
したがって、 X ≡ 6 (mod 7)
(4) 方程式・・・・・・
X3 ≡ 4 (mod 7)において、ind3(X3) ≡ ind3(4) (mod 6)
よって、 3×ind3(X) ≡ 4 (mod 6)
上式を満たす ind3(X) の値はないので、解なし。
上記の(4)に関連して、次の定理が知られている。
定理A p は有理素数とし、a は p で割り切れないものとする。
Xn ≡ a (mod p) が解を持つための必要十分条件は、
(n ,p−1)=d として、 indg(a) ≡ 0 (mod d)
(証明) indg(Xn) ≡ indg(a) (mod p−1) より、
n × indg(X) ≡ indg(a) (mod p−1)
この式を言い換えれば、解 indg(X) が存在するためには、不定方程式
n × M + (p−1) × N = indg(a)
を満たす整数 M(= indg(X))、N が存在することが必要十分である。
そのためには、互除法の理論により、 n と p−1 の最大公約数 d により
indg(a) が割り切れることが必要十分である。
よって、indg(a) ≡ 0 (mod d) でなければならない。 (証終)
(コメント) 上記の定理に照らせば、(4)では、ind3(4) = 4 で、(3 ,6)=3 から
ind3(4) ≡ 0 (mod 3)が成り立たないので、解は存在し得ないことが分かる。
・・・空舟さんより誤りの指摘を受け、修正済み(H24.2.29)
(5) 2次方程式・・・・・
2X2−3X+5 ≡ 0 (mod 7)において、両辺を4倍して、8X2−12X+20 ≡ 0 (mod 7)
すなわち、X2+2X−1 ≡ 0 (mod 7) となる。このとき、(X+1)2 ≡ 2 (mod 7)
ここで、(2 ,6)=2 で、ind3(2) ≡ 0 (mod 2)なので、解が存在する。
ind3((X+1)2) ≡ ind3(2) (mod 6) より、2・ind3(X+1) ≡ 2 (mod 6)
上式を満たす ind3(X+1) の値は、ind3(X+1) ≡ 1 、4 (mod 6)
したがって、 X+1 ≡ 3 、4 (mod 7) すなわち、X ≡ 2 、3 (mod 7)
(6) 累乗計算・・・・・
X ≡ 3100 (mod 7)において、
ind3(X) ≡ ind3(3100)≡ 100×ind3(3) ≡ 100 ≡ 4 (mod 6)
よって、 X ≡ 4 (mod 7)
(7) 指数方程式・・・・・
4x ≡ 3 (mod 7)において、ind3(4x) ≡ ind3(3) (mod 6) すなわち、
X・ind3(4) ≡ ind3(3) (mod 6) より、4・X ≡ 1 (mod 6)
ところが、(4 ,6)=2 で、1を割れないから、この方程式、すなわち、元の方程式には解
は存在しない。
4x ≡ 1 (mod 7)において、ind3(4x) ≡ ind3(1) (mod 6) すなわち、
X・ind3(4) ≡ ind3(1) (mod 6) より、4・X ≡ 0 (mod 6)
よって、 X ≡ 3 (mod 6)
(この2つの例からも分かるように、指数方程式は解を持つ場合と持たない場合があるので
要注意である。)
指数に関して、次の事実が知られている。
定理 有理素数 p は、p≠2 とする。このとき、任意の原始根 g に対して、
indg(−1) ≡ (p−1)/2 (mod p−1)
(証明) 原始根 g の定義より、 gp−1 ≡ 1 (mod p) が成り立つ。このとき、
gp−1−1 ≡ (g(p−1)/2−1)(g(p−1)/2+1) ≡ 0 (mod p) において、
g(p−1)/2−1 ≡ 0 (mod p)とはなり得ないので、
g(p−1)/2+1 ≡ 0 (mod p) より、 g(p−1)/2 ≡ −1 (mod p)
したがって、 indg(−1) ≡ (p−1)/2 (mod p−1) が成り立つ。 (証終)
例 指数表で、ind3(6) ≡ 3 (mod 6) であるが、6 ≡ −1 (mod 7)なので、
確かに、 ind3(−1) ≡ (7−1)/2 (mod 6) が成り立っている。
この定理を用いると、次の定理が得られる。
定理(ウィルソン) 有理素数 p に対して、 (p−1)!≡ −1 (mod p)
(証明) p=2 のときは、明らかに成り立つので、以下では、p>2 とする。
原始根 g を用いて、(p−1)! ≡ g0+1+2+・・・+(p-2) ≡ g(p-2)(p-1)/2 (mod p)
と書ける。上記の定理より、 g(p−1)/2 ≡ −1 (mod p) なので、p>2 より、
(p−1)! ≡ (−1)(p-2)≡ (−1)p≡ −1 (mod p) (証終)
単に、この定理を証明するだけだったら、次のようにした方が分かりやすいだろう。
(平成18年12月29日付け 加俊さんに質問されて見直しました!)
(別証) 素数 p が 2 の場合は、明らかに成り立つ。
奇素数 p に対して、フェルマーの定理より、1≦k≦p−1となる任意の整数 k に対して、
kp−1≡1 (mod p) が成り立つ。
したがって、多項式F(X)=Xp−1−1 において、
F(1)≡0 、 F(2)≡0 、・・・、 F(p−1)≡0 (mod p)
よって、 F(X)≡(X−1)(X−2)・・・(X−p+1) (mod p) と因数分解される。
そこで、X=0 を代入すると、 (−1)p−1・(p−1)!≡−1 (mod p)
p は奇数なので、 (−1)p−1=1
よって、(p−1)!≡−1 (mod p) が成り立つ。 (別証終)
(コメント) ウィルソンの定理は逆も成り立つ。 すなわち、
ウィルソンの定理の逆 (p−1)! ≡ −1 (mod p) ならば、p は有理素数
(証明) p が有理素数でないとすると、2つの自然数 m 、n (2 ≦ m
、n < p)を用いて、
p = mn と書ける。このとき、m は(p−1)! の約数で、(p−1)! +1 の約数にはなり
得ないので、p は、(p−1)! +1 の約数になり得ない。
これは、条件に矛盾する。 よって、p は素数でなければならない。 (証終)
(追記) 令和4年6月25日付け
例 p=7 のとき、 (p−1)!=6!=720 =103×7−1 ≡ −1 (mod 7)
よって、7は有理素数である。
上記の対偶は、
p は有理素数でなければ、(p-1)!≡-1 (mod p) は成り立たない
例 合成数の p=6 に対して、 (6-1)!=120≡0 (mod 6) である。
合成数の p=4 に対して、 (4-1)!=6≡2 (mod 4) である。
合成数の p=8 に対して、 (8-1)!=5040≡0 (mod 8) である。
上記のように、ウィルソンの定理を考えると、定理そのものが難しく思えるが、次のように
考えれば、ウィルソンの定理自体はごく単純なものである。
例えば、mod 11 において、
2×3×4×5×6×7×8×9
=(2×6)×(3×4)×(5×9)×(7×8)≡1×1×1×1=1
なので、 1×2×3×4×5×6×7×8×9×10≡10≡−1 となる。
上記では、 2×6≡1 、3×4≡1 、5×9≡1 、7×8≡1 であることが核心である。
ここで、11を法とする乗法表を考えてみる。
| \ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 2 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
| 3 |
3 |
6 |
9 |
1 |
4 |
7 |
10 |
2 |
5 |
8 |
| 4 |
4 |
8 |
1 |
5 |
9 |
2 |
6 |
10 |
3 |
7 |
| 5 |
5 |
10 |
4 |
9 |
3 |
8 |
2 |
7 |
1 |
6 |
| 6 |
6 |
1 |
7 |
2 |
8 |
3 |
9 |
4 |
10 |
5 |
| 7 |
7 |
3 |
10 |
6 |
2 |
9 |
5 |
1 |
8 |
4 |
| 8 |
8 |
5 |
2 |
10 |
7 |
4 |
1 |
9 |
6 |
3 |
| 9 |
9 |
7 |
5 |
3 |
1 |
10 |
8 |
6 |
4 |
2 |
| 10 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
上記の表には、1〜10までの数が何らかの順序で並んでいる。特に注意すべきは、全て
の行には必ず1が含まれているという点である。この表から、積が1となる2つの数を必ず見
いだすことが出来る。また、すべての行と列には、11より小さい数が丁度1回ずつ出現して
もいる。
さらに、1×1と10×10を結ぶ対角線上に、1が2度出現するが、それは対角線の両端に
おいてである。
このような性質は、一般の素数 p においても成り立つ。
合成数 p では、このようなことは必ずしも言えない。
例えば、p=6 のとき、p=11 の場合と明らかに異なる様相を示す。
| \ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 2 |
2 |
4 |
0 |
2 |
4 |
| 3 |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
| 4 |
4 |
2 |
0 |
4 |
2 |
| 5 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
このように考えると、ウィルソンの定理は、素数 p の乗算表からごく自然に導かれる結果
であると言える。
ウィルソンの定理は、1770年に英国の数学者・法律家のジョン・ウィルソン(1741〜1793)
により発表された。具体例を調べて、正しいことは確信していたが、証明は出来なかった。
証明は、仏の数学者ジョゼフ・ルイス・ラグランジュにより、発表されてまもなくなされた。
ライプニッツは、100年以上も前に、ウィルソンの定理を知っていたとも言われる。
定理(ライプニッツ) 有理素数 p に対して、 (p−2)!≡ 1 (mod p)
(証明) ウィルソンの定理より、
(p−1)! ≡ (p−1)(p−2)!≡−(p−2)!≡−1 (mod p)
なので、 (p−2)!≡ 1 (mod p) が成り立つ。 (証終)
先の定理A において、合同式が解を持つための条件を提示したが、原始根を用いてい
る点が気持ちが悪い。
定理Aは、次のように言い換えることが出来る。
定理B p は有理素数とし、a は p で割り切れないものとする。
Xn ≡ a (mod p) が解を持つための必要十分条件は、
(n ,p−1)=d、(p−1)/d=f として、 af ≡ 1 (mod p)
(証明) 定理A より、 解を持つための必要十分条件は、indg(a) ≡ 0 (mod d)
よって、 indg(a) =dk (k は自然数) と書ける。 このとき、定義より、
gdk ≡ a (mod p) となる。
ここで、両辺を f 乗すれば、 af ≡ g(p-1)k ≡ 1 (mod p)
逆に、af ≡ 1 (mod p)が成り立つとすると、原始根を g として、
indg(af) ≡ indg(1) (mod p−1) すなわち、 f ×indg(a) ≡ 0 (mod p−1)
ここで、 (n ,p−1)=d なので、 p−1=dh とおくと、h×indg(a) ≡ 0 (mod dh)
よって、indg(a) ≡ 0 (mod d) が得られる。 (証終)
方程式 Xn≡a (mod p) が
解を持つとき、 a を p の n 巾剰余
解を持たないとき、a を p の n 巾非剰余
という。 特に、n=2 のとき、平方剰余または平方非剰余といわれる。
(あっ!、やっと、これで前に述べた Legendre の記号 と話がつながった!)
以上の話をまとめると、方程式 Xn≡a (mod p) 、(n ,p−1)=d において、
a が p で割り切れないとき、
d=1 ならば、 a は必ず、n 巾剰余
d>1 ならば、 indg(a) が d で割り切れる a は、n 巾剰余で、その個数は、
(p−1)/d 個ある。
素数 p と互いに素な自然数の個数は、オイラーの関数 φ(n) で表されるが、上記の事実は、
φ(n) 個のうち丁度 1/d が、n 巾剰余になる
ことを示している。特に、n=2 のときは、d=2 なので、丁度半分ということになる。
空舟さんからのコメントです。(平成24年2月29日付け)
素数pに対する原始根を求めるのは、私の認識では、適当な数aをとって、a、a2、・・・を計
算してみて、もし原始根でなければ、そこに現れない他の数bで試して・・・という風にしらみつ
ぶしするしかないと認識しています。
砧 文夫 著『初等代数学』(1993)によると、原始根を具体的に求める一般的な方法はない
とのことで、ただ、1つさえ見つかれば、それを s として、p-1 と素な数qに対して、sq も原始
根という風に残りは得られます。
空舟さんからのコメントです。(平成24年2月29日付け)
「適当な数aをとって、a、a2、・・・を計算してみて・・・」と書きましたが、法997では、位数は
996の約数になるので、aが、997の原始根であることを確かめるには、996=2・2・3・83
に注
意して、a498≠1、a332≠1、a12≠1 かどうかを調べれば十分。a249≠±1、a166≠±1、
a6≠±1でも良い。
具体的な計算としては、a6、a83を計算して、それらに±1があれば終了。(a83)2、(a83)3 も
計算して、それらも±1でなければ、aは原始根。という風にすればだいぶ労力は減るでしょ
う。
せっかくなので、違う数 2・2・3・41+1=493 の原始根を考えてみます。493は実は素数で
はないことが判明し、17・29 ということは、493は原始根を持たないので、考察終わり。
さて、話を、もとの Legendre の記号 (a/p) に戻そう。
有理素数 p (p≠2)と、p で割り切れない整数 a において、上記の事実から、
 |
=(−1)indg(a) |
が成り立つ。
例 p=7 のとき、
| a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 指数 |
0 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
なので、
(1/7)=1 、(2/7)=1 、(3/7)=−1 、(4/7)=1 、(5/7)=−1 、(6/7)=−1
より、 1 、2 、4 が平方剰余、 3 、5 、7 が平方非剰余である。
または、上記の公式を用いないで、
12≡1 (mod 7) 、 32≡2 (mod 7) 、 52≡4 (mod 7)
からも分かる。
Legendre の記号 (a/p) の性質
(1) a ≡ b (mod p) ならば、 (a/p)≡(b/p)
(証明) a ≡ b (mod p) ⇔ indg(a) ≡ indg(b) (mod p−1) と
 |
= (−1)indg(a) |
の2つの事実から明らかであろう。 (証終)
(2) (abc・・・/p)=(a/p)(b/p)(c/p)・・・
(証明) indg(a×b) ≡ indg(a) + indg(b) (mod p−1) と
 |
= (−1)indg(a) |
の2つの事実から明らかであろう。 (証終)
定理(Euler の規準)
 |
≡ a(p-1)/2 (mod p) |
(証明) 上記で示した定理Bにより、X2 ≡ a (mod p) が解を持つための必要十分条
件は、 a(p - 1)/2 ≡ 1 (mod p) なので、
(a/p)=1 ならば、 a(p - 1)/2 ≡ 1 (mod p)
また、 (a/p)=−1 ならば、 ap - 1 ≡ 1 (mod p) において、
a(p - 1)/2 −1 は、p で割り切れないので、a(p - 1)/2 +1 が、p で割り切れる。
すなわち、 (a/p)=−1 ならば、 a(p - 1)/2 ≡ −1 (mod p)
以上から、定理が成り立つ。 (証終)
例 前述の例で、
(1/7)=1 、(2/7)=1 、(3/7)=−1 、(4/7)=1 、(5/7)=−1 、(6/7)=−1
であることを、指数表を活用して求めたが、上記の定理によれば、次のようにしても求める
ことが出来る。
13 ≡ 1 (mod 7)、 23 ≡ 1 (mod 7)、 33 ≡ −1 (mod 7)
43 ≡ 1 (mod 7)、 53 ≡ −1 (mod 7)、 63 ≡ −1 (mod 7)
(コメント) 7 で割った余りは、0、1、2、3、4、5、6 で、その平方を7で割った余りは、そ
れぞれ 0、1、4、2、2、4、1 となるので、0、1、2、4 の場合のみが平方剰余とな
る。指数というものを用いて、(a/p)を考えてきたが、何やら遠回りをしているような?
多分もっと素晴らしい応用があるのだろう。それを信じて先に進もう!
さて、当面の問題:
有理素数 p が、4で割って1余る数のとき、方程式 x2+y2 = p は、どのような解を持つ
のか?
に、ここで話を戻そう。
例 4で割って1余る有理素数 p としては、p=5、13、17、29、37、41、53、・・・
これらに対しては、
5=12+22 、13=22+32 、17=12+42 、29=22+52 、37=12+62
41=42+52 、53=22+72 、・・・
などと表され、取りあえずは解をもつことが予想される。
実は、次の定理が成り立つ。
定理(フェルマー・オイラーの素数定理)
有理素数 p が、4で割って1余る数のとき、方程式 x2+y2 = p は、有理整数解
を必ず持つ。
(この事実を初めて発見したのはフェルマー(1660年)だが、証明はオイラーが初めて(?)
与えたらしい。)
この定理から、4で割って1余る有理素数は、ガウスの整数としては、合成数となる。
(証明) Euler の規準から、 (−1/p)= (−1)(p-1)/2
ここで、p は4で割って1余る数なので、 (p−1)/2 は偶数。
よって、 (−1/p)=1 となり、 −1 は p の平方剰余となる。
したがって、 方程式 X2≡−1 (mod p) は有理整数解を持つ。
このとき、 X2+1=( X+ i )( X− i ) は、p で割り切れる。( i は、虚数単位)
ここで、 X− i と p の最大公約数を ε とおくと、ε は、p の約数なので、
ε = 1 または ε = p または ε = z (ただし、p=z・ ) の何れかが成り立つ。
) の何れかが成り立つ。
ε = 1 のとき、
X+ i 、 X− i ともに p と互いに素、すなわち、X2+1 は p と互いに素
これは、X2+1 が、p で割り切れることに矛盾。
ε = p のとき、X− i が p で割り切れることになり、矛盾。
したがって、 ε = z = a+b・i で、このとき、p=z・ でなければならない。
でなければならない。
ここで、p≠0 なので、 a≠±b より、 z と  は互いに同伴数にはなり得ない。
は互いに同伴数にはなり得ない。
以上から、
4で割って1余る有理素数は、ガウスの整数として、2つの異なる互いに共役な素数の積
として表される。 (証終)
上記証明で用いられた事実をさらに深めて、整数論の基本定理(平方剰余の相互法則)
が得られる。
定理
(1) 平方剰余の相互法則
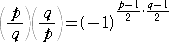
(2) 第一補充法則
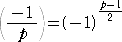
(3) 第二補充法則

この相互法則の最初の完全なる証明は、Gauss によるといわれる。
以下、工事中!