
らすかるさんのHPに「三角関数表」が掲載されていた。その表を眺めていたら、次の値に
ついては手計算で求めてみようという雰囲気にさせてくれる。他の値は見通しをつけるのが
難しそう...。
0°、30°、45°、60°、90°の5つについては、自明としていいだろう。
15°、75°については、加法定理の活用例として適切だろう。
ただ、次のような図形的解法も存在する。
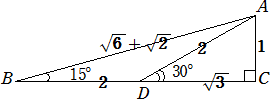
図より、 sin15°=1/(
cos15°=(2+
tan15°=1/(2+
18°、22.5°、36°、54°、67.5°、72°についても図形を利用して求めることが
出来る。
○ 22.5°、67.5°の場合
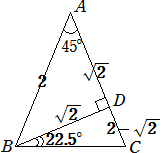
図より、 tan22.5°=(2−
ここで、 BC=2√(2−
sin22.5°=(2−
cos22.5°=
○ 18°、36°、54°、72°の場合(→ 参考:「正5角形の作図と折り紙」)
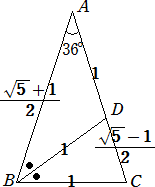
図より、 sin18°=(
ここで、 1−(
cos18°=√(10+2
tan18°={(
同様にして、 cos36°=(
ここで、 1−(
sin36°=√(10−2
tan36°={√(10−2
あと、図形で求められる角度は、いくつ...。
(追記) 令和7年10月11日付け
次の東北大学 後期文系(2000)の問題は、sin15°、cos15°、tan15°の計算に
新しい視点を与えてくれる。
問題 ∠ABC=∠ACB=15° である三角形ABCについて、線分ABを点Aの側へ延
長して、その上に点Dをとり、AD=BC となるようにする。このとき、次の問いに答えよ。
(1) sin15°、cos15°、tan15° を求めよ。
(2) ∠ADC=θ とおくとき、sinθの値を求めよ。
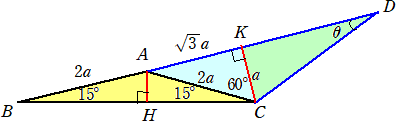
(解)(1) 上図において、 BC2=a2+(2+
BC=(
よって、 sin15°=1/(
cos15°=(
tan15°=1/(
(2) 上図において、 AD=BC=4acos15°=(
このとき、 KD=(
CD2=(
よって、 sinθ=1/√{12−6
(コメント) 問題文のヒントが秀逸ですね。そのヒントがなければ、通常次のように解くだろう
と思います。
(1) AB=AC=1 としても一般性を失わない。Aより底辺BCに垂線を下ろし、その足
をHとおく。このとき、AH=sin15°、BC=2cos15° である。
余弦定理より、 4cos215°=1+1−2cos150°=2+
よって、 2cos15°=(
また、 (1/2)・(
sin15°=1/(
このとき、 tan15°=(
(追記) 令和7年11月1日付け
次の東北大学 後期文系(2001)の問題は、文字の消去に気が付けば容易だろう。
問題 a は定数で、−90°<t<90°とする。2点
P((1/2)sint+cos2t,tant) 、Q(sin2t+acost,3sint−2cost+a+2)
がある t に対して同じ点となるとき、定数 a の値およびそのときの t の値を求めよ。
(解) (1/2)sint+cos2t=sin2t+acost
tant=3sint−2cost+a+2 がある t に対して成り立つ。
a=tant−3sint+2cost−2 を第1式に代入して、
(1/2)sint+cos2t=sin2t+(tant−3sint+2cost−2)cost
から、 (1/2)sint+cos2t−sin2t=2sintcost+sint−3sintcost+2cos2t−2cost
すなわち、 sintcost−(1/2)sint+2cost−1=0
よって、 (cost−1/2)(sint+2)=0 より、 sint+2≠0 から、 cost=1/2
−90°<t<90°より、 t=±60°
t=60° のとき、
a=tant−3sint+2cost−2=
t=−60° のとき、
a=tant−3sint+2cost−2=−
(追記) 令和7年11月19日付け
次の東北大学 後期文系(2002)の問題は、測量問題である。
問題 水平な地面に垂直に塔が建っている。目の高さ1.5mの人が地面のある地点Aに
立って塔の頂上を見上げると、仰角がθであった。ただし、θ>0°とする。この人が塔に
向かって160m近づいて見上げると、仰角が2θになった。さらに100m近づいて見上げ
ると、仰角が4θになった。以下の問いに答えよ。
(1) cosθの値を求めよ。
(2) 塔の高さを求めよ。
(3) 同じ人が地点Aから塔に向かって何m近づくと、塔の頂上を見上げる仰角が3θになるか。
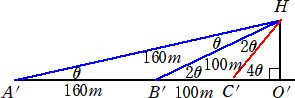
(解)(1) △HB’C’において、余弦定理より、
1002=1002+1602−2・100・160cos2θ
すなわち、 2・100・cos2θ=160 より、 cos2θ=4/5
2cos2θ−1=4/5 より、 cosθ=3/
(2) OH’=100sin4θ=200sin2θcos2θ
ここで、cos2θ=4/5 より、 sin2θ=3/5 なので、
OH’=200(3/5)(4/5)=96
よって、塔の高さは、 OH’+1.5=97.5(m)
(3) 塔の頂上を見上げる仰角が3θになる地点をDとし、目線の位置をD’とする。
∠B’HD’=θ より、∠D’HC’=θ なので、 線分HD’は∠B’HC’の2等分線となる。
よって、 B’D’ : D’C’=160 : 100=8 : 5 となる。
このことから、 B’D’=100×(8/13)=800/13 となるので、
地点Aから塔に向かって、 160+800/13=2880/13(m) 近づけばよい。 (終)
以下、工事中!