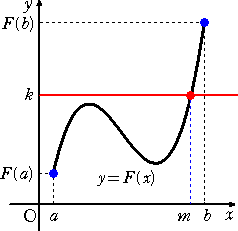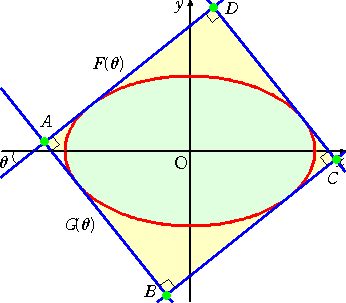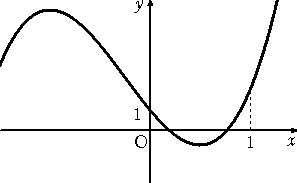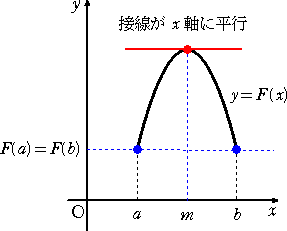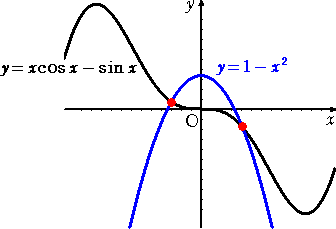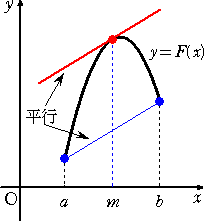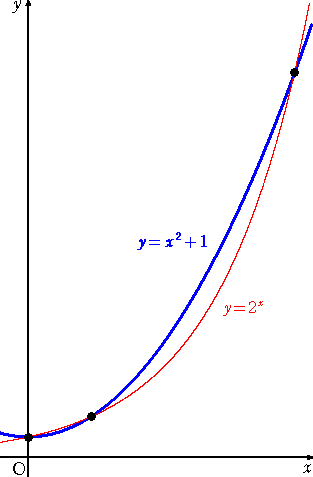幚悢夝偺屄悢 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂曽掱幃偑嬶懱揑偵夝偗偰丄夝偑捈愙揑偵媮傔傜傟傞応崌偼摿偵堄幆偟側偄偑丄栤戣傪
峫偊傞忋偱丄夝偑偁傞斖埻偵懚嵼偡傞偙偲傪抦傝偨偄応崌偑墲乆偵偟偰偁傞偙偲偼丄擔崰
宱尡偟偰偄傞偲偙傠偱偁傞丅
丂偙偺傛偆側応崌偵妶桇偡傞岞幃偲偟偰偼丄
丂拞娫抣偺掕棟丂丄儘乕儖偺掕棟丂丄暯嬒抣偺掕棟
側偳偑抦傜傟偰偄傞丅
丂偙傟傜偼壗傟傕乽悢妛嘨乿偱妛傇傕偺偱偁傞偑丄擔杮偺崅峑惗偺傎偲傫偳偑丄偙傟傜傪妛
偽偢偟偰悢妛嫵掱傪廔椆偟偰偟傑偭偰偄傞丅偙偺偙偲偼丄旕忢偵巆擮側偙偲偱偁傞丅
丂嶐擔丄擔杮戝妛暥棟妛晹偺悢妛嫵幒偐傜丄乽僒儅乕僗僋乕儖乿傊偺偍桿偄偺埬撪偑撏偄
偨丅悢妛壢憂愝俆侽廃擭偲偄偆偙偲偱丄椺擭偲庒姳堎側傞嵜偟偲側傞傜偟偄丅
丂暉揷戱惗丂愭惗偵傛傞乽拞娫抣偺掕棟偲偦偺墳梡乿偲偄偆墘戣偺島墘偑梊掕偝傟偰偄傞偲
偺偙偲偱惀旕嶲壛偟偨偐偭偨偑丄惗憺傕偆梊掕偑擖偭偰偟傑偭偰偄偰丄崱擭偼巆擮側偑傜寚
惾偣偞傞傪摼側偄丅
丂偙偺儁乕僕偱偼丄暉揷愭惗偺島墘偵巚偄傪抷偣偰丄忋婰偺庬乆偺岞幃偵偮偄偰丄傑偲傔
偰偄偙偆偲巚偆丅
拞娫抣偺掕棟
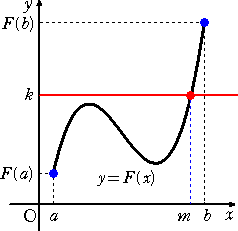 |
乮俙乯丂娭悢 俥乮倶乯偼暵嬫娫乵 倎 丆倐 乶偱楢懕偲偡傞丅
丂偙偺偲偒丄
丂丂 俥乮倎乯 偲 俥乮倐乯 偺娫偺擟堄偺悢 倠 偵懳偟偰丄
丂丂丂丂丂丂 俥乮倣乯亖 倠
丂偲側傞 倣 乮 倎亙倣亙倐 乯偑懚嵼偡傞丅
丂丂戝妛庴尡偱偼丄傓偟傠師偺傛偆側昞尰偺曽偑傛偔
丂巊傢傟傞傛偆偩丅 |
丂乮俛乯丂娭悢 俥乮倶乯 偼丄暵嬫娫 乵 倎 丆倐 乶 偱楢懕偲偟丄 俥乮倎乯丒俥乮倐乯亙侽丂偲偡傞丅
丂丂丂偙偺偲偒丄丂 俥乮倣乯亖 侽丂丂偲側傞 倣 乮 倎亙倣亙倐 乯偑懚嵼偡傞丅
丂忋婰偺掕棟偱丄丂乮俙乯仺乮俛乯偼丄堈偟偄偩傠偆丅
丂俥乮倎乯丒俥乮倐乯亙侽丂傛傝丄俥乮倎乯偲俥乮倐乯偺娫偵丄侽 偑偁傞偺偱丄乮俛乯偼乮俙乯傛傝柧傜偐偱偁傞丅
摨條偵丄乮俛乯仺乮俙乯偼丄俧乮倶乯亖俥乮倶乯亅倣 偲偍偗偽傛偄丅偙偺偲偒丄俧乮倎乯丒俧乮倐乯亙侽丂傛傝丄
乮俙乯偼丄柧傜偐偵惉傝棫偮丅
丂偙偺拞娫抣偺掕棟偺徹柧偼幚悢榑偲枾愙偵娭學偟偰偄傞偨傔崅峑偺庼嬈偱偼捠忢側偝
傟側偄丅忋婰偺傛偆側恾偱擺摼偝偣丄愢摼偟偰偄傞偺偑幚忬偱偁傞丅
丂偙偙偱偼丄崅峑惗儗儀儖傪堄幆偟偰丄乮俛乯偺曽偺棯徹傪帋傒傞偙偲偵偟傛偆丅
乮棯徹乯丂堦斒惈傪幐偆偙偲側偔丄丂俥乮倎乯亙侽丂丄俥乮倐乯亜侽丂偲偟偰傛偄丅
丂偄傑丄俙亖乷 倶 伕乵 倎 丆倐 乶乥俥乮倶乯亙侽 乸 偲偄偆廤崌傪峫偊傞丅
丂柧傜偐偵丄丂俙 偼丄乵 倎 丆倐 乶偺晹暘廤崌偱偁傞丅
丂擟堄偺 倶 伕俙 偵懳偟偰丄 倶 亙 倐丂偑惉傝棫偮丅乮偙偺偲偒丄廤崌 俙 偼忋偵桳奅偲偄偆乯
丂偦偙偱丄俛亖乷 倷 伕俼乥擟堄偺 倶 伕俙 偵懳偟偰丄 倶 亝 倷 乸 偲偄偆廤崌傪峫偊傞丅
乮偙偺偲偒丄廤崌 俛 傪廤崌 俙 偺忋奅偲偄偆乯
丂倐 伕俛丂側偺偱丄廤崌 俛 偼嬻廤崌偱偼側偄丅
偦偙偱丄丂俠亖俼亅俛丂偲偍偔偲丄倎 伕俙伡俠丂側偺偱丄俠 傕嬻廤崌偱偼側偔丄
丂俼亖俛伨俠丂丄丂俛伩俠亖冇丂偑惉傝棫偪丄偝傜偵丄
丂擟堄偺丂們 伕俠丂丄 倐 伕俛丂偵懳偟偰丄丂們 亙 倐
偱偁傞偺偱丄廤崌 俛 丄俠 偼幚悢偺愗抐傪梌偊傞丅
乮梫偼丄幚悢慡懱偑俛傑偨偼俠偺偳偪傜偐堦曽偵暘偐偨傟傞偲偄偆偙偲両乯
丂幚悢偺楢懕偺岞棟乮偪傚偭偲丄偙傟偼崅峑惗儗儀儖傪墇偊傞偐側丠乯偐傜丄
丂廤崌 俛 偺嵟彫抣丂傑偨偼丂廤崌 俠 偺嵟戝抣
偺偳偪傜偐堦曽偩偗偑懚嵼偡傞丅
丂偄傑丄廤崌 俠 偺嵟戝抣 倣乫 偑懚嵼偡傞傕偺偲壖掕偡傞丅
偙偺偲偒丄倣乫 偼廤崌 俛 偵偼懏偝側偄偺偱丄丂倣乫 亙 倸丂偲側傞 倸 伕俙 偑懚嵼偡傞丅
丂傑偨丄幚悢偺鈌枾惈乮梫偼丄偁傞悢偵偄偔傜偱傕嬤偄悢偑偲傟傞偲偄偆偙偲両乯傛傝丄
丂倣乫 亙 値 亙 倸丂偲側傞 値 伕俼 偑懚嵼偡傞丅偙偺偲偒丄柧傜偐偵丄値 偼廤崌 俛 偵偼懏偝側
偄偺偱丄値 伕俠丂偱偁傞丅偙傟偼丄倣乫 偑廤崌 俠 偺嵟戝抣偱偁傞偙偲偵柕弬偡傞丅
丂埲忋偐傜丄丂廤崌 俛 偺嵟彫抣偺傒偑懚嵼偡傞丅偙偺嵟彫抣傪丄倣 偲偍偔丅
乮偙偺傛偆側 倣 偺偙偲傪丄廤崌 俙 偺忋尷偲偄偄丄倱倳倫俙 偲昞偡丅乯
丂倐 伕俛丂側偺偱丄丂倣 亝 倐丂偱偁傞偑丄幚偼丄偝傜偵徻偟偔丄丂倣 亙 倐丂偑惉傝棫偮丅
丂幚嵺偵丄丂俥乮倶乯偼楢懕偱丄丂俥乮倐乯亜侽丂傛傝丄丂倶0亙倐丂偱偁傞傛偆側 倐 偺嬤偔偺抣 倶0 偱
昁偢 俥乮倶0乯亜侽丂偲側傝丄 倶0 偼丄廤崌 俙 偺忋奅偲側傞丅
偙偺偲偒丄丂倣 偺嵟彫惈偐傜丄丂倣 亝 倶0 偱丄倶0 亙 倐丂傛傝丄丂倣 亙 倐丂偲側傞丅
偝傜偵丄丂俥乮倣乯亖侽丂偑惉傝棫偮丅
丂幚嵺偵丄丂俥乮倣乯亙侽丂偲壖掕偡傞偲丄丂倣 伕俙丂偱丄 俥乮倶乯偼楢懕傛傝丄
丂倣亙倶0亙倐丂偱偁傞傛偆側 倣 偺嬤偔偺抣 倶0 偱丄丂俥乮倶0乯亙侽丂偲側傝丄丂倶0 伕俙丂偑惉傝棫
偮丅偙偺偙偲偼丄廤崌 俙 偺忋尷偱偁傞 倣 傛傝傕戝偒偄廤崌 俙 偺梫慺 倶0 偑懚嵼偟偨偙偲偵
側傝丄偙傟偼柕弬偱偁傞丅傛偭偰丄丂俥乮倣乯亞侽丂偱偁傞丅
丂偙偙偱丄丂俥乮倣乯亜侽丂偲壖掕偡傞丅偙偺応崌傕傗偼傝丄 俥乮倶乯偼楢懕偱丄丂俥乮倣乯亜侽丂傛傝丄
丂倶0亙倣丂偱偁傞傛偆側 倣 偺嬤偔偺抣 倶0 偱昁偢 俥乮倶0乯亜侽丂偲側傝丄 倶0 偼丄廤崌 俙 偺忋
奅偲側傞丅
丂偙偺偲偒丄丂倶0 伕俛丂側偺偱丄丂倣 亝 倶0丂偱偁傞偑丄偙偺偙偲偼丄倶0亙倣丂偱偁傞偙偲偵柕
弬偡傞丅
丂埲忋偐傜丄丂俥乮倣乯亖侽丂偑惉傝棫偮丅丂乮徹廔乯
乮僐儊儞僩乯丂堦墳丄徹柧傜偟偒傕偺傪彂偄偰偼傒偨傕偺偺丄乽乣偱偁傞両乿傕偺傪曄側榑棟偱
丂丂丂丂丂丂屻墴偟偟偰偄傞偩偗偺傛偆側丏丏丏偦傫側暤埻婥丅恾偱棟夝偝傟傟偽廫暘偲嵞擣
丂丂丂丂丂丂幆偟傑偟偨丅
丂忋婰偺徹柧傪尒偰傕暘偐傞傛偆偵丄徹柧偦偺傕偺偑幚悢偺楢懕惈偵棈傫偱偄傞偺偱丄偙
傟傪堦斒偺崅峑惗偵嫵偊傞偙偲偼摓掙晄壜擻偵嬤偄偲幚姶偱偒傞丅
丂傕偺偺偮偄偱偵丄拞娫抣偺掕棟乮俙乯偵懳偡傞丄師偺傛偆側徹柧傕偁偘偰偍偙偆丅
乮徹柧乯丂丒丒丒丂僇儞僩乕儖偺俀暘朄乮嬫暘弅彫朄乯傪梡偄偨徹柧
丂嬫娫 俲0亖乵 倎 丆倐 乶丂偲偟丄丂俲値亖乵 倎値 丆倐値 乶丂傪師偺傛偆偵峔惉偡傞丅
偨偩偟丄丂倎0亖倎 丂丄倐0亖倐丂偱丄丂俥乮倎乯亙倠亙俥乮倐乯丂偲偡傞丅
偄傑丄丂倣0亖乮倎0亄倐0乯/俀丂偲偍偒丄
丂俥乮倣0乯亞倠丂側傜偽丄丂倎1亖倎0 丂丄倐1亖倣0
丂俥乮倣0乯亙倠丂側傜偽丄丂倎1亖倣0 丂丄倐1亖倐0
偲偍偔丅偄偢傟偵偟偰傕丄丂俥乮倎1乯亙倠亙俥乮倐1乯丂偑惉傝棫偮丅埲壓丄摨條丅
丂偙偺偲偒丄丂倎0亝倎1亝丒丒丒亝倎値亝丒丒丒亝倐値亝丒丒丒亝倐1亝倐0丂偱丄
丂倐値亅倎値亖乮倐亅倎乯/俀値
傛傝丄悢楍乷倎値乸偼扨挷憹壛偱忋偵桳奅丄悢楍乷倐値乸偼扨挷尭彮偱壓偵桳奅側偺偱丄偲傕偵
廂懇偟丄倐値亅倎値丂仺丂侽丂偐傜丄摨偠嬌尷抣 倣 傪傕偮丅
丂俥乮倎値乯亙倠亙俥乮倐値乯丂傛傝丄嫴傒寕偪偺尨棟偐傜丄
丂俥乮倣乯亝倠亝俥乮倣乯丂偡側傢偪丄丂俥乮倣乯亖倠丂偲側傞丅丂乮廔乯
乮僐儊儞僩乯丂偙偪傜偺曽偑崅峑惗岦偒偱丄帇妎揑偵暘偐傝傗偡偄偐側丠
丂偙偺掕棟偺墳梡椺偲偟偰偼丄師偺傛偆側栤戣偑婎杮揑偱偁傠偆丅
椺丂曽掱幃 俀倶亅俁倶亖侽丂偼丄侽 偲 侾 偺娫偵夝傪帩偮偙偲傪帵偣丅
乮夝乯丂丂俥乮倶乯亖俀倶亅俁倶丂偲偍偔偲丄俥乮倶乯偼丄暵嬫娫 乵 侽 丆 侾 乶 偱楢懕偱偁傞丅
傑偨丄丂俥乮侽乯丒俥乮侾乯亖乮俀0亅俁丒侽乯乮俀1亅俁丒侾乯亖侾丒乮亅侾乯亖亅侾亙侽
傛偭偰丄拞娫抣偺掕棟傛傝丄曽掱幃 俀倶亅俁倶亖侽丂偼丄侽 偲 侾 偺娫偵夝傪帩偮丅乮廔乯
丂忋婰偺椺偼捖晠揑偱偁傞偑丄師偺傛偆側椺偼巃怴側墳梡椺偱偁傠偆丅巹帺恎丄偦偺峫偊
曽偵媣乆偺怴慛偝傪姶偠偨丅
椺丂恖偺曕偔懍偝偼暯嬒偱暘懍俉侽倣偲尵傢傟傞丅偨偩丄曕偔娐嫬乮摴偺忬嫷傗婥暘側偳乯偱
丂丂懡彮偼慜屻偡傞丅偄傑丄偁傞恖偑丄係侽侽倣偺摴偺傝傪
俆暘偱曕偄偨偲偡傞丅偙偺偲偒丄偙
丂丂偺恖偼丄偙偺摴偺傝偺偁傞俉侽倣偺嬫娫傪偒偭偪傝侾暘偱曕偄偰偄傞偙偲傪帵偣丅
乮夝乯丂曕偒巒傔偰偐傜偺嫍棧傪
倶 倣偲偟丄倶 倣 偐傜倶亄俉侽 倣 傑偱偺摴偺傝傪曕偔偺偵梫偡
傞帪娫傪丄俥乮倶乯 偲偍偔丅偙偺偲偒丄俥乮倶乯 偼丄暵嬫娫乵侽丆俁俀侽乶偱楢懕偱偁傞丅
丂偙偺偲偒丄丂俥乮侽乯亄俥乮俉侽乯亄俥乮侾俇侽乯亄俥乮俀係侽乯亄俥乮俁俀侽乯亖俆丂偑惉傝棫偮丅
偙傟傛傝丄丂俥乮侽乯丄俥乮俉侽乯丄俥乮侾俇侽乯丄俥乮俀係侽乯丄俥乮俁俀侽乯偺慡偰偑侾傛傝彫偝偄偙偲偼側偄丅
摨條偵丄慡偰偑侾傛傝戝偒偄偙偲傕側偄丅
丂傛偭偰丄丂偁傞悢 倎 偲 倐 偑懚嵼偟偰丄丂俥乮倎乯亝侾亝俥乮倐乯丂偲側傞丅
丂偟偨偑偭偰丄拞娫抣偺掕棟偵傛傝丄丂俥乮們乯亖侾丂偲側傞 們 偑 倎 偲倐 偺娫偵懚嵼偡傞丅
丂偙偺偲偒丄丂們 偐傜偺俉侽倣 偺嬫娫傪僉僢僠儕 侾暘娫偱曕偄偰偄傞偙偲偵側傞丅乮廔乯
丂懠偵柺敀偄墳梡椺偲偟偰偼丄師偺栤戣偑偁偘傜傟傞丅乮暯惉俀侽擭侾侾寧俀擔晅偗偱捛婰乯
栤丂戣丂丂懭墌偵奜愙偡傞惓曽宍偑懚嵼偡傞偙偲傪帵偣丅
乮夝乯丂揔摉偵暯峴堏摦丄夞揮傪巤偟偰丄懭墌偺曽掱幃偼丄
丂丂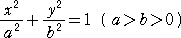
偲偟偰傕堦斒惈偼幐傢側偄丅偦偺懭墌偵俀慻偺暯峴側愙慄偑悅捈偵岎傢偭偰偄傞丅
丂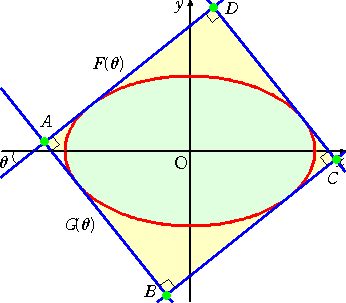
丂忋恾偺挿曽宍俙俛俠俢偵偍偄偰丄捈慄俙俢偑 倶 幉偺惓偺岦偒偲側偡妏傪兤偲偡傞丅
兤偺斖埻偲偟偰丄丂侽亝兤亝兾/俀丂偲偟偰傛偄丅
丂俙俢亖俥乮兤乯丄俙俛亖俧乮兤乯丂偼丄兤偺楢懕娭悢偱偁傞丅
偦偙偱丄俫乮兤乯亖俥乮兤乯亅俧乮兤乯丂偲偍偔偲丄娭悢 俫乮兤乯 偼丄暵嬫娫 乵 侽 丆 兾/俀 乶 偱楢懕
偲側傞丅丂偙偙偱丄
丂俫乮侽乯亖俥乮侽乯亅俧乮侽乯亖俀倐亅俀倎丂丄俫乮兾/俀乯亖俥乮兾/俀乯亅俧乮兾/俀乯亖俀倎亅俀倐
側偺偱丄丂俫乮侽乯丒俫乮兾/俀乯亖亅係乮倎亅倐乯2亙侽丂偑惉傝棫偮丅
丂傛偭偰丄拞娫抣偺掕棟傛傝丄丂俫乮倣乯亖侽丂乮倎亙倣亙倐乯丂偲側傞 倣 偑懚嵼偡傞丅
丂偙偺偲偒丄丂俥乮倣乯亖俧乮倣乯丂偱丄挿曽宍俙俛俠俢偼惓曽宍偲側傞丅丂乮廔乯
乮僐儊儞僩乯丂墌偺応崌偼惓曽宍偺懚嵼偼帺柧偱偡偑丄懭墌偺応崌傕懚嵼偡傞偲偼柺敀偄偱
丂丂丂丂丂丂偡偹両
丂偙偺拞娫抣偺掕棟偼丄恾傪梡偄偰丄婔壗妛揑僀儊乕僕偑捦傒傗偡偄偼偢側偺偵丄尰栶偺
棟宯庴尡惗偵偼側偐側偐怹摟偟偯傜偔丄栤戣夝朄偵廲墶柍恠偵巊偄偙側偡傛偆偵側傞傑偱
偼帄擄偺嬈偺傛偆偱偁傞丅
乮捛婰乯丂暯惉俀侽擭俈寧俀俁擔晅偗偱丄摉俫俹偺宖帵斅乽弌夛偄偺愹乿偵摉俫俹偑偄偮傕偍悽榖
丂丂丂丂丂偵側偭偰偄傞 倸倠係俁偝傫偐傜拞娫抣偺掕棟偵偮偄偰僐儊儞僩傪捀偄偨丅
丂屖忬楢寢側埵憡嬻娫 倃 偐傜幚悢偺廤崌 俼 傊偺楢懕幨憸側傜偽丄倃偺擟堄偺俀揰傪寢傇
楢懕嬋慄傪 乵 侽 丆侾 乶偱僷儔儊乕僞偯偗傟偽丄乵 侽 丆侾 乶偐傜 俼傊偺楢懕娭悢偑偱偒傞偺偱丄
傗偼傝丄拞娫抣偺掕棟偑惉傝棫偪傑偡丅
丂屖忬楢寢側埵憡嬻娫偺楢懕幨憸偵傛傞憸偼丄傗偼傝屖忬楢寢側偺偱乮憡庤偺嬻娫偺憡懳
埵憡傪偄傟傟偽乯丄拞娫抣偺掕棟偲摨偠傛偆側昞尰偑偱偒傞偐傕偟傟傑偣傫丅屖忬楢寢側埵
憡嬻娫偺楢懕幨憸偱峫偊傞偺偑丄拞娫抣偺掕棟偺嵟傕堦斒揑側姶偠偼偟傑偡丅
丂楢懕幨憸偲偼丄偮側偑偭偨傕偺傪愗傝棧偝側偄丄偲偄偆偺偑杮幙偱丄偦傟傪偄傠偄傠側尵梩
偱昞尰偟偰偄傞偩偗偲偄偆姶偠丅娭悢偱偼戝彫娭學傪帩偪弌偟偰昞尰偟偰偄傞偩偗偱偡偹丅
丂拞娫抣偺掕棟偼丄傕偭偲堦斒揑側宍偱師偺傛偆偵弎傋傜傟傞丅
堦斒揑側拞娫抣偺掕棟
丂楢寢側埵憡嬻娫 倃 偐傜幚悢偺廤崌 俼 傊偺楢懕幨憸傪 俥 偲偡傞偲丄
丂倎伕倃丂丄倐伕倃丂偵懳偟偰丄俥乮倎乯亙倠亙俥乮倐乯 側傜偽丄俥乮倣乯亖倠丂偲側傞 倣伕倃丂偑
懚嵼偡傞丅
乮棯徹乯丂廤崌 俙亖乷 倷伕俥乮倃乯乥 倷亙倠 乸丂丄俛亖乷 倷伕俥乮倃乯乥 倷亜倠 乸丂偲偍偔偲丄
丂俥乮倎乯伕俙丂丄丂俥乮倐乯伕俛丂側偺偱丄丂俙 丄俛 偼丄嬻偱側偄奐廤崌偱偁傞丅
偙偙偱丄傕偟丄倠 偑廤崌 俥乮倃乯 偺梫慺偱側偄偲偡傞偲丄
丂俥乮倃乯亖俙伨俛丂偱丂俙伩俛亖冇丂偲側傝丄俥乮倃乯偼俀偮偺嫟捠晹暘傪帩偨側偄奐廤崌偱旐暍
偝傟傞丅偙傟偼丄俥乮倃乯偑楢寢偱偁傞偙偲偵柕弬偡傞丅
偟偨偑偭偰丄丂倠 偼廤崌 俥乮倃乯 偺梫慺偲側傝丄俥乮倣乯亖倠丂偲側傞 倣伕倃 偑懚嵼偡傞丅乮棯徹廔乯
乮僐儊儞僩乯丂屖忬楢寢側傜偽楢寢偱偁傞偑丄媡偼惉傝棫偨側偄丅乽楢寢乿偲偄偆彮偟備傞偄忦
丂丂丂丂丂丂審偱拞娫抣偺掕棟偑惉傝棫偮偙偲偼嬃偒偱偡偹両
桳柤側椺戣丂丂扨埵墌 俽 偐傜幚悢偺廤崌 俼 傊偺楢懕娭悢傪 俥 偲偡傞偲丄
丂俥乮倣乯亖俥乮亅倣乯 偲側傞 倣伕俽丂偑懚嵼偡傞偙偲傪帵偣丅
乮僐儊儞僩乯丂尨揰懳徧側偁傞揰偱丄娭悢偺抣偑堦抳偡傞応崌偑偁傞偲偼柺敀偄惈幙偱偡偹両
乮椺戣偺夝摎乯丂乵 侽 丆侾 乶偐傜幚悢偺廤崌 俼 傊偺楢懕娭悢 俧 傪丄
丂俧乮倶乯亖俥乮 們倧倱兾倶 丆 倱倝値兾倶 乯亅俥乮 亅們倧倱兾倶 丆 亅倱倝値兾倶 乯
丂偲掕媊偡傞丅偙偺偲偒丄
丂俧乮侽乯亖俥乮 侾 丆侽 乯亅俥乮 亅侾 丆侽 乯丂丄俧乮侾乯亖俥乮 亅侾 丆侽 乯亅俥乮 侾 丆侽 乯
偱偁傞丅丂偙偙偱丄丂俧乮侽乯亖侽丂側傜偽丄丂倣亖乮 侾 丆侽 乯丂偲偍偗偽傛偄丅
丂俧乮侽乯亗侽丂側傜偽丄丂俧乮侽乯丒俧乮侾乯亖亅乮俥乮 侾 丆侽 乯亅俥乮 亅侾 丆侽 乯乯2亙侽
側偺偱丄拞娫抣偺掕棟偵傛傝丄丂俧乮倶0乯亖侽丂偲側傞 侽亙倶0亙侾丂偑懚嵼偡傞丅
偙偺偲偒丄丂倣亖乮 們倧倱兾倶0 丆 倱倝値兾倶0 乯丂偲偍偗偽丄俥乮倣乯亖俥乮亅倣乯偑惉傝棫偮丅丂乮廔乯
丂拞娫抣偺掕棟偺墳梡偲偟偰丄師偺晄摦揰掕棟傕桳柤偱偁傞丅屆偔偼丄憗堫揷戝妛棟岺妛
晹偺擖帋栤戣偲偟偰弌戣偝傟偨偙偲傕偁傞偺偱丄偛懚偠偺曽傕懡偄偙偲偩傠偆丅
晄摦揰掕棟
丂俥乮倶乯 偼暵嬫娫 乵 侽 丆侾 乶 偱楢懕偱丄丂侽亝俥乮倶乯亝侾 偲偡傞丅
偙偺偲偒丄俥乮倣乯亖倣 偲側傞 倣 偑懚嵼偡傞丅乮偙偺傛偆側 倣 偺偙偲傪丄娭悢 俥乮倶乯 偺晄摦揰偲尵偆両乯
乮徹柧乯丂俧乮倶乯亖俥乮倶乯亅倶 偲偍偔偲丄俧乮倶乯偼丄暵嬫娫 乵 侽 丆 侾 乶 偱楢懕偱偁傝丄
丂俧乮侽乯亖俥乮侽乯亞侽丂丂丄丂俧乮侾乯亖俥乮侾乯亅侾亝侽
偙偙偱丄丂俧乮侽乯亖侽丂偺偲偒偼丄丂倣亖侽丂偲偍偗偽傛偄丅
丂俧乮侾乯亖侽丂偺偲偒偼丄丂倣亖侾丂偲偍偗偽傛偄丅
丂俧乮侽乯亜侽丂丄丂俧乮侾乯亙侽丂偺偲偒偼丄拞娫抣偺掕棟傛傝丄
丂俧乮倣乯亖侽丂偡側傢偪丂俥乮倣乯亖倣丂偲側傞 倣乮侽亙倣亙侾乯偑懚嵼偡傞丅
傛偭偰丄壗傟偵偟偰傕丄俥乮倣乯亖倣丂偲側傞 倣乮侽亝倣亝侾乯偑懚嵼偡傞丅丂乮徹廔乯
乮僐儊儞僩乯丂偙偺晄摦揰掕棟傪丄揤嵥悢妛幰偺壀丂寜愭惗偼丄摉帪偺撧椙彈巕戝侾擭惗偵
丂丂丂丂丂懳偟偰丄師偺傛偆偵愢柧偟偨偲偄偆丅
丂挿偝 侾倣 偺僑儉傂傕偺椉抂傪椉庤偱帩偭偰堷偭挘傞偲偒丄僑儉傂傕偺偁傞侾揰偱丄巒傔偺
埵抲偐傜旝恛傕偢傟側偄揰偑懚嵼偡傞丅偦偺揰偑晄摦揰偱偁傞丏丏丏丅
丂忋婰偺栤戣傕丄僺儞偲挘偭偨僑儉傂傕偱偼側偔儓儗儓儗偺僑儉傂傕偑丄尨揰偲乮 侾 丆 侾 乯偵
妵傝晅偗傜傟偰偄傞偲峫偊傟偽丄壀丂寜丂愭惗偺尵傢傫偲偟偨偙偲偑揱傢偭偰偒傑偡偹両
丂幚悢夝偺懚嵼傪庡挘偡傞応崌偵嫮椡偲巚傢傟偨拞娫抣偺掕棟傕師偺傛偆側栤戣偵偼旕
椡偦偆偵尒偊傞丅
椺丂俁師曽掱幃 係倶3亄俁倶2亅俇倶亄侾亖侽丂偼丄侽 偲 侾 偺娫偵夝傪帩偮偙偲傪帵偣丅
丂俥乮倶乯亖係倶3亄俁倶2亅俇倶亄侾丂偲偍偔偲丄丂俥乮侽乯亖侾亜侽丂丄丂俥乮侾乯亖俀亜侽丂側偺偱丄娙扨偵
偼拞娫抣偺掕棟傪揔梡偝偣偰偔傟側偄丅
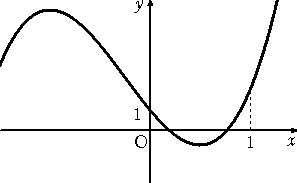 |
丂丂僌儔僼傪昤偄偰丄
丂丂丂丂俥乮侾/俀乯亖亅俁/係亙侽
丂偱偁傞偙偲偑嶡偣傜傟傞偺偱丄拞娫抣偺掕
丂棟傪暵嬫娫乵侽丆侾/俀乶偵揔梡偡傟偽栤戣偼
丂夝寛偡傞偑丄偁傑傝旤偟偄夝朄偲偼尵偊側偄丅
|
丂偙偺傛偆側応崌偼丄師偺儘乕儖偺掕棟偑桳岠偱偁傞丅
儘乕儖乮俼倧倢倢倕乯偺掕棟丂丒丒丒丂侾俇俋侾擭丂暓偺 俵倝們倛倕倢丂俼倧倢倢倕 (1652乣1719) 偵傛傝敪昞丅
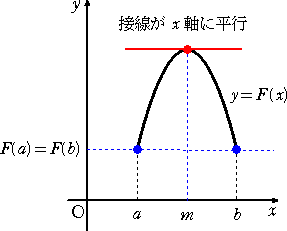 |
丂娭悢 俥乮倶乯 偼丄暵嬫娫 乵 倎 丆倐 乶 偱楢懕
偱丄奐嬫娫 乮 倎 丆倐 乯 偱旝暘壜擻偲偡傞丅
丂丂偙偺偲偒丄丂俥乮倎乯亖俥乮倐乯丂側傜偽丄
丂丂丂俥乫乮倣乯亖 侽 偲側傞 倣 乮 倎亙倣亙倐 乯
偑懚嵼偡傞丅 |
丂偙偺掕棟傪忋婰偺栤戣偵揔梡偟偰傒傛偆丅
乮夝乯丂俥乮倶乯亖倶4亄倶3亅俁倶2亄倶丂偲偍偔偲丄丂俥乮侽乯亖俥乮侾乯亖侽丂偑惉傝棫偮丅
丂俥乮倶乯偼丄暵嬫娫 乵 侽 丆 侾 乶 偱楢懕偱偁傝丄奐嬫娫 乮 侽 丆 侾 乯 偱旝暘壜擻側偺偱丄
丂儘乕儖偺掕棟傛傝丄丂俥乫乮倣乯亖侽丂偲側傞 倣 乮侽亙倣亙侾乯偑懚嵼偡傞丅
傛偭偰丄係倣3亄俁倣2亅俇倣亄侾亖侽丂偲側傞 倣 乮侽亙倣亙侾乯偑懚嵼偡傞偺偱丄戣堄偼帵偝傟
偨丅 丂乮廔乯
乮僐儊儞僩乯丂儘乕儖偺掕棟偲偄偆偲崱傑偱暯嬒抣偺掕棟偺嫶搉偟揑懚嵼偲巚偭偰偄傑偟偨偑丄
丂丂丂丂丂堄奜側妶梡朄傪抦偭偰姶摦偟傑偟偨丅
丂撉幰偺偨傔偵丄楙廗栤戣傪巆偟偰偍偙偆丅
栤丂戣丂丂係師曽掱幃 俆倶4亅係倶亄侾亖侽丂偼丄侽 偲 侾 偺娫偵夝傪帩偮偙偲傪帵偣丅
乮夝乯丂俥乮倶乯亖倶5亅俀倶2亄倶丂偲偍偔偲丄丂俥乮侽乯亖俥乮侾乯亖侽丂偑惉傝棫偮丅
丂俥乮倶乯偼丄暵嬫娫 乵 侽 丆 侾 乶 偱楢懕偱偁傝丄奐嬫娫 乮 侽 丆 侾 乯 偱旝暘壜擻側偺偱丄
丂儘乕儖偺掕棟傛傝丄丂俥乫乮倣乯亖侽丂偲側傞 倣 乮侽亙倣亙侾乯偑懚嵼偡傞丅
傛偭偰丄俆倣4亅係倣亄侾亖侽丂偲側傞 倣 乮侽亙倣亙侾乯偑懚嵼偡傞偺偱丄戣堄偼帵偝傟偨丅乮廔乯
丂偙偺儘乕儖偺掕棟傪梡偄傞偲丄偄傠偄傠柺敀偄偙偲偑暘偐傞傜偟偄丅
乮侾乯丂儘乕儖偺掕棟偱丄乽 俥乮倎乯亖俥乮倐乯亖侽 乿偲偄偆摿庩側応崌傪憐掕偡傞偲丄師偺偙偲偑惉
丂傝棫偮偙偲偼柧傜偐偩傠偆丅丂乮俥乮倎乯亖俥乮倐乯亖侽丂偲側傞 倎丄倐 傪俥乮倶乯偺楇揰偲偄偆乯
丂俥乮倶乯偺楇揰偑丄倎 丄倐 偺偲偒丄俥乫乮倶乯偺楇揰偼丄倎 丄倐 偺娫偵偁傞
丂俥乮倶乯偺楇揰偑丄値屄偁傞偲偒丄俥乫乮倶乯偺楇揰偼丄彮側偔偲傕 値亅侾屄偁傞
丂偙偺帠幚傪梡偄傞偲丄夝偺屄悢偑摿掕偝傟傞応崌偑偁傞丅
椺丂曽掱幃丂倶2亄倶們倧倱倶亅倱倝値倶亅侾亖侽丂偼幚悢夝傪丄偪傚偆偳 俀屄偩偗帩偮偙偲傪帵偣丅
乮夝乯丂俥乮倶乯亖倶2亄倶們倧倱倶亅倱倝値倶亅侾丂偲偍偔偲丄俥乮倶乯偼丄暵嬫娫 乵 亅兾/俀 丆
兾/俀 乶 偱楢
懕偱偁傝丄奐嬫娫 乮 亅兾/俀 丆 兾/俀 乯 偱旝暘壜擻偱偁傞丅
丂傑偨丄丂俥乮亅兾/俀乯亖兾2/係亜侽丂丄丂俥乮侽乯亖亅侾亙侽丂丄俥乮兾/俀乯亖兾2/係亅俀亜侽
側偺偱丄拞娫抣偺掕棟偵傛傝丄曽掱幃丂倶2亄倶們倧倱倶亅倱倝値倶亅侾亖侽丂偼幚悢夝傪彮側偔偲傕
俀屄帩偮丅
丂偄傑丄曽掱幃丂倶2亄倶們倧倱倶亅倱倝値倶亅侾亖侽丂偺幚悢夝偑俁屄埲忋偲壖掕偡傞丅
偙偺偲偒丄丂儘乕儖偺掕棟傛傝丄曽掱幃 俥乫乮倶乯亖俀倶亅倶倱倝値倶亖侽丂偼丄俀屄埲忋偺幚悢夝傪
帩偮丅
偲偙傠偑丄柧傜偐偵丄丂俀倶亅倶倱倝値倶亖侽丂懄偪丄丂倶乮俀亅倱倝値倶乯亖侽丂偼丄倶亖侽 偺侾屄偟偐夝傪
帩偨側偄丅丂偙傟偼丄柕弬偱偁傞丅
傛偭偰丄曽掱幃丂倶2亄倶們倧倱倶亅倱倝値倶亅侾亖侽丂偺幚悢夝偼丄偪傚偆偳 俀屄偱偁傞丅丂丂乮廔乯
乮僐儊儞僩乯丂偙偺傛偆側儘乕儖偺掕棟偺巊偄曽偼丄巹帺恎弶傔偰偺宱尡偱怴慛偱偟偨両
丂倷亖侾亅倶2丂偲丂倷亖倶們倧倱倶亅倱倝値倶丂偺僌儔僼傪昤偐偣傞偲丄夝偺屄悢偼柧傜偐偩偑丄僌儔僼
偱偼枴傢偊側偄憉夣姶偑姶偠傜傟傑偟偨両奆偝傫傕摨姶偐側丠
丂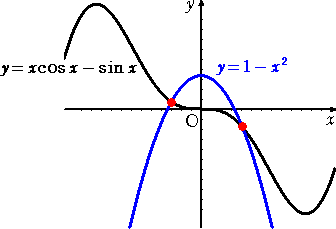
乮俀乯丂儘乕儖偺掕棟偲偄偆偲丄傗偼傝丄乽 俥乮倎乯亖俥乮倐乯亖侽 乿偲偄偆忦審偱揔梡偡傞応崌偑懡
丂偄傛偆側丏丏丏幚姶両
丂娭悢 俥乮倶乯 偼丄暵嬫娫 乵 倎 丆倐 乶 偱楢懕偱丄奐嬫娫 乮 倎 丆倐 乯 偱旝暘壜擻偲偡傞丅
偙偺偲偒丄丂俥乮倎乯亖俥乮倐乯亖侽丂側傜偽丄
丂俥乮倣乯亖 俥乫乮倣乯丂偲側傞 倣 乮 倎亙倣亙倐 乯偑懚嵼偡傞丅
丂捈偖偵偼怣偠傜傟側偄傛偆側寢壥偱偡偹両偱傕丄儘乕儖偺掕棟偑偙偺怣偠傜傟側偄寢壥偵
偍杗晅偒傪梌偊傞傫偩傛偹丏丏丏丅
椺偊偽丄丂俥乮倶乯亖倶2亅俀倶丂偲偍偔偲丄
丂俥乮倶乯偼丄暵嬫娫 乵 侽 丆俀 乶 偱楢懕丄奐嬫娫 乮 侽 丆俀 乯 偱旝暘壜擻偱丄
丂俥乮侽乯亖俥乮俀乯亖侽丂偑惉傝棫偮丅偙偺偲偒丄忋婰偺寢壥偼丄
丂曽掱幃丂俥乮倶乯亖俥乫乮倶乯丂偡側傢偪丄丂倶2亅俀倶亖俀倶亅俀丂偑丄侽亙倶亙俀丂偵夝傪帩偮偙偲傪
庡挘偡傞傕偺偱偁傞丅
丂幚嵺偵丄丂倶2亅係倶亄俀亖侽丂偺夝偼丄倶亖俀亇 丂偱丄侽亙俀亅
丂偱丄侽亙俀亅 亙俀丂偱偁傞丅
亙俀丂偱偁傞丅
丂偙傟偑丄偄偮傕惉傝棫偮偲偄偆偐傜嬃偒偩丅
乮徹柧乯丂俧乮倶乯亖倕亅倶丒俥乮倶乯丂偲偍偔丅乮仼丂偙偺傛偆側抲偒曽偼丄恞忢偱偼側偄偱偡傛偹丠乯
丂偙偺偲偒丄丂娭悢 俧乮倶乯 偼丄暵嬫娫 乵 倎 丆倐 乶 偱楢懕丄奐嬫娫 乮 倎 丆倐 乯 偱旝暘壜擻偱丄
偟偐傕丄丂俧乮倎乯亖俧乮倐乯亖侽丂偑惉傝棫偮丅
丂傛偭偰丄儘乕儖偺掕棟傛傝丄丂俧乫乮倣乯亖侽丂偲側傞 倣 乮 倎亙倣亙倐 乯偑懚嵼偡傞丅
丂俧乫乮倶乯亖亅倕亅倶丒俥乮倶乯亄倕亅倶丒俥乫乮倶乯亖亅倕亅倶乷 俥乮倶乯亅俥乫乮倶乯 乸丂傛傝丄
丂俧乫乮倣乯亖亅倕亅倣乷 俥乮倣乯亅俥乫乮倣乯 乸亖侽
偲側傞 倣 乮 倎亙倣亙倐 乯偑懚嵼偡傞丅丂倕亅倣亗侽丂側偺偱丄埲忋偐傜丄
丂俥乮倣乯亅俥乫乮倣乯亖侽丂懄偪丄丂俥乮倣乯亖俥乫乮倣乯丂偲側傞 倣 乮 倎亙倣亙倐 乯偑懚嵼偡傞丅乮徹廔乯
丂偙偙偱丄愭偵弎傋偨儘乕儖偺掕棟偺棯徹傪梌偊偰偍偙偆丅
乮棯徹乯丂倷 幉曽岦偵暯峴堏摦偝偣偰丄乽俥乮倎乯亖俥乮倐乯亖侽乿偲偟偰傕堦斒惈偼幐傢傟側偄丅
丂暵嬫娫 乵 倎 丆倐 乶 偱峆摍揑偵 俥乮倶乯亖侽丂側傜偽丄掕棟偼柧傜偐偵惉傝棫偮丅
偦偙偱丄暵嬫娫 乵 倎 丆倐 乶 偱峆摍揑偵 俥乮倶乯偼丄侽丂偱偼側偄偲偟偰傛偄丅
偙偺偲偒丄丂俥乮們乯亗侽丂偲側傞 們 偑懚嵼偡傞丅
丂揔摉偵乮亅侾乯傪妡偗傞偙偲偵傛偭偰丄俥乮們乯亜侽丂偲偟偰傕堦斒惈偼幐傢傟側偄丅
暵嬫娫 乵 倎 丆倐 乶 偵偍偄偰丄 俥乮倶乯偺嵟戝抣傪 俵 偲偡傞偲丄丂俵亖俥乮倣乯 偲側傞 倣 偑懚嵼
偡傞丅偙偺偲偒丄丂侽亙俥乮們乯亝俵丂偱丄丂俥乮倎乯亖俥乮倐乯亖侽丂傛傝丄丂倎 亙 倣 亙 倐丂偱偁傞丅
偝傜偵丄俥乮倶乯偼丄奐嬫娫 乮 倎 丆倐 乯 偱旝暘壜擻偱丄廫暘彫側傞 倛 偵懳偟偰忢偵丄
丂俥乮倣亄倛乯亅俥乮倣乯亝侽
偱偁傞偺偱丄
丂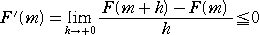
偐偮
丂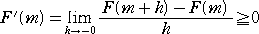
偑惉傝棫偮丅傛偭偰丄丂俥乫乮倣乯亖侽丂偲側傞丅丂乮棯徹廔乯
丂儘乕儖偺掕棟偑帵偝傟傟偽丄暯嬒抣偺掕棟傪帵偡偙偲偼梕堈偱偁傞丅
暯嬒抣偺掕棟乮俵倕倎値丂倁倎倢倳倕丂俿倛倕倧倰倕倣乯丂丒丒丒丂俰丏俴丏俴倎倗倰倎値倗倕丂乮1736乣1813乯
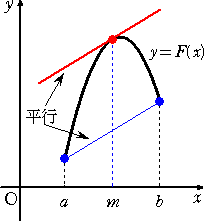 |
丂丂娭悢 俥乮倶乯 偼丄暵嬫娫 乵 倎 丆倐 乶 偱楢懕偱丄奐嬫
丂娫 乮 倎 丆倐 乯偱旝暘壜擻偲偡傞丅
丂丂偙偺偲偒丄
丂丂丂丂丂丂丂丂
丂偲側傞 倣 乮 倎亙倣亙倐 乯偑懚嵼偡傞丅
|
乮徹柧乯丂
丂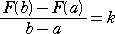
偲偍偒丄娭悢 俧乮倶乯亖俥乮倶乯亅俥乮倎乯亅倠乮倶亅倎乯丂傪峫偊傞偲丄娭悢 俧乮倶乯偼丄
暵嬫娫 乵 倎 丆倐 乶 偱楢懕偱丄奐嬫娫 乮 倎 丆倐 乯偱旝暘壜擻偱偁傝丄丂俧乮倎乯亖俧乮倐乯丂偲側傞丅
傛偭偰丄儘乕儖偺掕棟傛傝丄俧乫乮倣乯亖侽丂偡側傢偪丄丂倠亖俥乫乮倣乯丂偲側傞
倣 乮 倎亙倣亙倐 乯
偑懚嵼偡傞丅丂乮徹廔乯
丂偙偺暯嬒抣偺掕棟傪梡偄傞偲丄師偺帠幚偑尩枾偵徹柧偝傟傞丅
丂娭悢 俥乮倶乯 偑丄暵嬫娫 乵 倎 丆倐 乶 偱旝暘壜擻偱丄忢偵丄俥乫乮倶乯亖侽丂側傜偽丄
娭悢 俥乮倶乯 偼丄偙偺暵嬫娫 乵 倎 丆倐 乶 偱掕悢偱偁傞丅
乮徹柧乯丂倎亙倶亝倐丂偱偁傞擟堄偺 倶 偵懳偟偰丄丂俥乮倶乯亖俥乮倎乯亄俥乫乮倣乯乮倶亅倎乯丂偲側傞
倣
乮 倎亙倣亙倶 乯偑懚嵼偡傞丅丂俥乫乮倣乯亖侽丂側偺偱丄忢偵丄丂俥乮倶乯亖俥乮倎乯丂偲側傞丅
傛偭偰丄暵嬫娫 乵 倎 丆倐 乶 偱忢偵丄丂俥乮倶乯偼掕悢 偲側傞丅丂乮徹廔乯
丂忋婰偺帠幚偼丄晄掕愊暘偺寁嶼傗旝暘曽掱幃偺棟榑偺婎慴偲側傞傕偺偱偁傞丅
丂師偺帠幚傕娭悢偺憹尭敾掕偵偼寚偐偣側偄傕偺偱偁傞丅
丂娭悢 俥乮倶乯 偑丄暵嬫娫 乵 倎 丆倐 乶 偱旝暘壜擻偱丄忢偵丄俥乫乮倶乯亜侽丂側傜偽丄
娭悢 俥乮倶乯 偼丄偙偺暵嬫娫 乵 倎 丆倐 乶 偱憹壛偡傞丅
乮徹柧乯丂倎亝倶1亙倶2亝倐丂偱偁傞擟堄偺 倶1丄倶2 偵懳偟偰丄
丂俥乮倶2乯亅俥乮倶1乯亖俥乫乮倣乯乮倶2亅倶1乯丂偲側傞 倣 乮 倎亙倣亙倶 乯偑懚嵼偡傞丅
丂俥乫乮倣乯亜侽丂側偺偱丄忢偵丄丂俥乮倶2乯亅俥乮倶1乯亜侽丂偲側傞丅
傛偭偰丄暵嬫娫 乵 倎 丆倐 乶 偱忢偵丄丂俥乮倶乯偼憹壛娭悢偱偁傞丅丂乮徹廔乯
丂暯嬒抣偺掕棟偼師偺傛偆側宍偵傕曄宍偝傟傞丅
丂娭悢 俥乮倶乯 偼丄暵嬫娫 乵 倎 丆倐 乶 偱楢懕偱丄奐嬫娫 乮 倎 丆倐 乯偱旝暘壜擻偲偡傞丅
丂偙偺偲偒丄丂俥乮倐乯亖俥乮倎乯亄倛丒俥乫乮倎亄兤倛乯丂丂乮偨偩偟丄倛亖倐亅倎丂乯 偲側傞
兤 乮 侽亙兤亙侾 乯偑懚嵼偡傞丅
丂師偺傛偆側栤戣偑丄暯嬒抣偺掕棟傪妛廗偟偨屻偵嫵壢彂偵嵹偭偰偄偨丅惓捈偵崘敀偡傞
偲丄崱偱偼壗偱傕側偄偑丄崅峑帪戙偼栿傕暘偐傜偢偵寁嶼偟偰偄偨傛偆偵巚偆丅壗偐偙傟傑
偱偺悢妛偺寁嶼偲偼偪傚偭偲堘偆傛偆側崅彯偝傪姶偠偰晘嫃偑崅偔姶偠傜傟偨丅
椺丂娭悢 倷亖倶2丂偵偮偄偰丄嬫娫 乵侾丆俀乶偵暯嬒抣偺掕棟傪揔梡偟丄倣 丄兤偺抣傪媮傔傛丅
乮夝乯丂係亅侾亖俀倣乮俀亅侾乯丂傛傝丄丂倣亖俁/俀
丂倣亖侾亄兤乮俀亅侾乯丂傛傝丄丂兤亖侾/俀丂乮廔乯
椺丂娭悢 倷亖侾/倶丂偵偮偄偰丄嬫娫 乵侾丆俀乶偵暯嬒抣偺掕棟傪揔梡偟丄倣
丄兤偺抣傪媮傔傛丅
乮夝乯丂侾/俀亅侾亖乮亅侾/倣2乯乮俀亅侾乯丂傛傝丄丂倣亖
丂倣亖侾亄兤乮俀亅侾乯丂傛傝丄丂兤亖 亅侾丂乮廔乯
亅侾丂乮廔乯
丂偙偺 俴倎倗倳倰倎値倗倕 偺暯嬒抣偺掕棟偼丄俠倎倳們倛倷 偺暯嬒抣偺掕棟偵奼挘偝傟傞丅
俠倎倳們倛倷 偺暯嬒抣偺掕棟
丂娭悢 俥乮倶乯丄俧乮倶乯 偼丄暵嬫娫 乵 倎 丆倐 乶 偱楢懕偱丄奐嬫娫 乮
倎 丆倐 乯偱旝暘壜擻
偲偟丄偝傜偵丄奐嬫娫 乮 倎 丆倐 乯偱丄 俧乫乮倶乯亗侽丂偲偡傞丅
偙偺偲偒丄
丂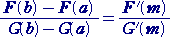
偲側傞 倣 乮 倎亙倣亙倐 乯偑懚嵼偡傞丅
乮僐儊儞僩乯丂暘曣偲暘巕偱丄嫟捠偺 倣 偑庢傟傞偙偲傪庡挘偡傞傕偺偱僗僑僀偱偡偹両
乮徹柧乯丂奐嬫娫 乮 倎 丆倐 乯偱丄 俧乫乮倶乯亗侽丂側偺偱丄丂俧乮倎乯亗俧乮倐乯丂偱偁傞丅偦偙偱丄
丂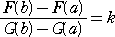
偲偍偄偰丄丂俫乮倶乯亖俥乮倶乯亅俥乮倎乯亅倠乮俧乮倶乯亅俧乮倎乯乯丂偲偡傞偲丄娭悢 俫乮倶乯偼丄
暵嬫娫 乵 倎 丆倐 乶 偱楢懕偱丄奐嬫娫 乮 倎 丆倐 乯偱旝暘壜擻偱偁傝丄丂俫乮倎乯亖俫乮倐乯丂偲側傞丅
傛偭偰丄儘乕儖偺掕棟傛傝丄俫乫乮倣乯亖侽丂偡側傢偪丄丂俥乫乮倣乯亅倠俧乫乮倣乯亖侽丂偲側傞 倣
乮 倎亙倣亙倐 乯偑懚嵼偡傞丅丂乮徹廔乯
丂柧傜偐偵丄暯嬒抣偺掕棟偼丄俠倎倳們倛倷 偺暯嬒抣偺掕棟偵偍偄偰丄俧乮倶乯亖倶丂偺応崌偱偁
傞丅
丂暯嬒抣偺掕棟傪偝傜偵奼挘偡傟偽丄俿倎倷倢倧倰 偺掕棟傊偲恑揥偡傞偑丄偙偺儁乕僕偺僥乕儅
乽幚悢夝偺屄悢乿偐傜傑偡傑偡墦偔側偭偰偟傑偆偺偱丄俿倎倷倢倧倰 偺掕棟偵娭偡傞榖戣偼暿側儁
乕僕偵埾偹偰丄杮戣偵栠傞偙偲偵偟傛偆丅
栤丂戣丂曽掱幃 俀x亅倶2亅侾亖侽丂偺幚悢夝偺屄悢傪媮傔傛丅
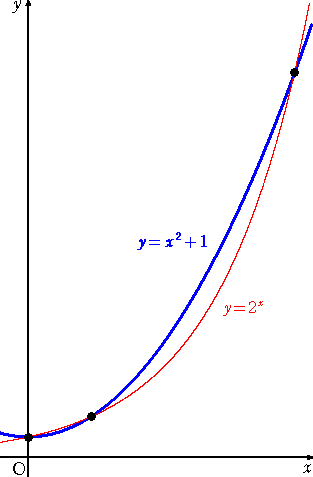 |
丂丂丂僌儔僼昤夋僜僼僩傪妶梡偡傟偽丄
丂丂丂丂丂倷亖俀倶
丂丂丂丂偲
丂丂丂丂丂倷亖倶2亄侾
丂丂偺岎傢傝偺條巕偐傜丄幚悢夝偺屄悢
丂丂偼丄俁屄偱偁傞偲悇嶡偝傟傞偑丄偙偺傛
丂丂偆側夝朄偼丄偙偺儁乕僕偺庯巪偵斀偡
丂丂傞偙偲偱偁傞丅 |
乮夝乯丂娭悢 俥乮倶乯亖俀x亅倶2亅侾丂偲偍偔偲丄俥乮倶乯偼楢懕偱旝暘壜擻側娭悢偱偁傞丅
丂倶亙侽丂偵偍偄偰丄俀x亙侾丂丄倶2亄侾亜侾丂側偺偱丄丂俥乮倶乯亖侽丂偲側傞幚悢夝偼懚嵼偟側偄丅
傑偨丄倶亖侽丂偺偲偒丄丂俥乮侽乯亖侽丂偲側傞偺偱丄倶亖侽 偼幚悢夝偱偁傞丅
丂倶亖侾丂偺偲偒丄丂俥乮侾乯亖侽丂偲側傞偺偱丄倶亖侾 偼幚悢夝偱偁傞丅
侽亙倶亙侾丂偵偍偄偰丄丂俥乮倶乯亖侽丂偲側傞幚悢夝 們 偑懚嵼偡傞偲壖掕偡傞丅
丂偙偺偲偒丄儘乕儖偺掕棟傛傝丄丂俥乫乮倶乯亖侽丂偲側傞 倣1丄倣2 乮倣1亙倣2 乯偑懚嵼偡傞丅
丂偝傜偵丄儘乕儖偺掕棟傛傝丄丂俥乭乮倣乯亖侽丂偲側傞 倣丂乮倣1亙倣亙倣2 乯偑懚嵼偡傞丅
偲偙傠偑丄丂俥乫乮倶乯亖俀x倢倧倗俀亅俀倶丂丄丂俥乭乮倶乯亖俀x乮倢倧倗俀乯2亅俀丂傛傝丄
丂侽亙倣亙侾丂偵偍偄偰丄丂俥乭乮倣乯亖俀倣乮倢倧倗俀乯2亅俀亙俀乮乮倢倧倗俀乯2亅侾乯亙侽丂側偺偱丄偙傟
偼柕弬偱偁傞丅
丂傛偭偰丄侽亙倶亙侾丂偵偍偄偰丄丂俥乮倶乯亖侽丂偲側傞幚悢夝偼懚嵼偟側偄丅
丂傑偨丄丂侾亙倶亙俀丂偵偍偄偰丄
丂俥乭乮倶乯亖俀x乮倢倧倗俀乯2亅俀亙係乮倢倧倗俀乯2亅俀亖乮倢倧倗係乯2亅俀亙侽
側偺偱丄丂俥乫乮倶乯 偼扨挷偵尭彮偟丄丂俥乫乮侾乯亖俀倢倧倗俀亅俀亖俀乮倢倧倗俀亅侾乯亙侽 傛傝丄
侾亙倶亙俀丂偵偍偄偰丄丂俥乫乮倶乯亙侽丂偲側傝丄俥乮倶乯 偼扨挷偵尭彮偡傞丅
丂俥乮侾乯亖侽丂側偺偱丄丂侾亙倶亙俀丂偵偍偄偰丄丂俥乮倶乯亙侽丂偲側傞丅
傛偭偰丄丂侾亙倶亙俀丂偵偍偄偰丄丂俥乮倶乯亖侽丂偲側傞幚悢夝偼懚嵼偟側偄丅
丂偙偙偱丄丂俥乮俀乯亖係亅係亅侾亖亅侾亙侽丂丄丂俥乮俆乯亖俁俀亅俀俆亅侾亖俇亜侽丂側偺偱丄
俀亙倶亙俆丂偵偍偄偰丄丂俥乮倶乯亖侽丂偲側傞幚悢夝偑彮側偔偲傕侾屄懚嵼偡傞丅
丂偄傑丄俀亙倶亙俆丂偵偍偄偰丄丂俥乮倶乯亖侽丂偲側傞幚悢夝偑俀屄埲忋懚嵼偡傞傕偺偲偟丄
偦偺偆偪偺俀屄傪 們1丄們2 乮 們1亙們2 乯偲偡傞丅
丂偙偺偲偒丄侾亙倶亙俆丂偵偍偄偰丄儘乕儖偺掕棟傛傝丄
丂俥乫乮倶乯亖侽丂偲側傞 倣1丄倣2 乮侾亙倣1亙們1亙倣2亙們2 乯偑懚嵼偡傞丅
偟偐傞偵丄丂 俥乫乮倶乯亖侽丂偼丄丂侽亙倶亙侾丂偲丂侾亙倶丂偵侾屄偢偮偟偐夝傪帩偨側偄偺偱丄
偙傟偼柕弬偱偁傞丅
丂傛偭偰丄丂俀亙倶亙俆丂偵偍偄偰丄丂俥乮倶乯亖侽丂偲側傞幚悢夝偑侾屄懚嵼偡傞丅
丂倶亜俆丂偵偍偄偰丄
丂俥乭乮倶乯亖俀x乮倢倧倗俀乯2亅俀亜俁俀乮倢倧倗俀乯2亅俀亖俀乮係乮倢倧倗係乯2亅侾乯亜侽
傛傝丄丂俥乫乮倶乯 偼扨挷偵憹壛偟丄丂俥乫乮俆乯亖俁俀倢倧倗俀亅侾侽亖侾俇倢倧倗係亅侾侽亜侽 側偺偱丄
倶亜俆丂偵偍偄偰丄丂俥乮倶乯亜侽丂偲側傞丅
傛偭偰丄倶亜俆丂偵偍偄偰丄丂俥乮倶乯亖侽丂偲側傞幚悢夝偼懚嵼偟側偄丅
埲忋偐傜丄媮傔傞曽掱幃偺幚悢夝偺屄悢偼丄俁屄偱偁傞丅丂乮廔乯
乮僐儊儞僩乯丂偐側傝僔價傾偵昡壙偟側偄偲偄偗側偄偺偱丄偪傚偭偲僔儞僪僀偱偡偹両僌儔僼偺曽
丂丂丂丂丂丂偑妝偩乣両両偱傕丄忋婰偺夝摎丄傕偭偲惍棟偝傟側偄偺偐側丠
栤丂戣丂幚悢學悢偺 値 師偺懡崁幃 俥乮倶乯亖倎0倶値亄倎1倶値-1亄丒丒丒亄倎値-1倶亄倎値丂偑丄憡堎側
傞 値亄侾 屄偺楇揰傪帩偰偽丄侽亝倠亝値丂側傞慡偰偺 倠 偵懳偟偰丄倎倠亖侽 偲側傞偙偲傪帵偣丅
乮夝乯丂帺慠悢 値 偵娭偡傞悢妛揑婣擺朄偱帵偡丅
値亖侾丂偺偲偒丄丂倎0丒兛亄倎1亖侽丂丄丂倎0丒兝亄倎1亖侽丂乮扐偟丄丂兛亗兝乯丂傛傝丄
丂倎0丒乮兛亅兝乯亖侽
兛亗兝丂側偺偱丄丂倎0亖侽丂丂偙傟傛傝丄丂倎1亖侽
傛偭偰丄丂柦戣偼丄 値亖侾 偺偲偒惉傝棫偮丅
値亖倠乮 倠 偼擟堄偺帺慠悢乯偺偲偒丄柦戣偑惉傝棫偮傕偺偲壖掕偡傞丅
丂値亖倠亄侾 偺偲偒傪峫偊傞丅丂偡側傢偪丄幚悢學悢偺 倠亄侾 師偺懡崁幃
丂俥乮倶乯亖倎0倶倠亄1亄倎1倶倠亄丒丒丒亄倎倠倶亄倎倠亄1
偑丄憡堎側傞 倠亄俀 屄偺楇揰傪帩偮偲偒傪峫偊傞丅偙偺偲偒丄儘乕儖偺掕棟傛傝丄
幚悢學悢偺 倠 師偺懡崁幃 俥乮倶乯亖乮倠亄侾乯倎0倶倠亄倠倎1倶倠-1亄丒丒丒亄倎倠 偑丄
憡堎側傞 倠亄侾 屄偺楇揰傪帩偮丅婣擺朄偺壖掕偐傜丄
丂乮倠亄侾乯倎0亖侽丂丄丂倠倎1亖侽丂丄丂丒丒丒丂丄丂倎倠亖侽
偙偺偲偒丄丂倎0亖侽丂丄丂倎1亖侽丂丄丂丒丒丒丂丄丂倎倠亖侽丂偱丄偝傜偵丄丂倎倠亄1亖侽丂偲側傞丅
傛偭偰丄値亖倠亄侾 偺偲偒傕柦戣偼惉傝棫偮丅
埲忋偐傜丄悢妛揑婣擺朄偵傛傝丄慡偰偺帺慠悢 値 偵偮偄偰丄柦戣偼惉傝棫偮丅丂乮廔乯
乮僐儊儞僩乯丂偙傟偼丄乽悢妛嘦乿偱妛傇乽峆摍幃乿偺尨棟偱偡偹両偙傟傑偱偑儘乕儖偺掕棟偺
丂丂丂丂丂丂斖醗偵側傞偲偼嬃偒偱偡丅
乮捛婰乯丂椷榓俇擭俈寧俁擔晅偗
丂幚悢夝偺屄悢偺栤戣偲偔傟偽丄愙慄偺杮悢偺栤戣偑偡偖憐婲偝傟傞丅師偺栤戣偼丄搶杒
戝妛棟宯乮侾俋俉侽乯偱弌戣偝傟偨傕偺偱偁傞丅
戞侾栤丂丂嬋慄 倷亖倶3亄倎倶2亄倐 偺愙慄偱尨揰傪捠傞傕偺偑俁杮偁傞偲偡傞丅倎丄倐 偺枮偨偡
丂丂忦審傪媮傔丄揰乮倎丆倐乯偺懚嵼偡傞斖埻傪恾帵偣傛丅
乮夝乯丂愙揰偺 倶 嵗昗傪 倲 偲偡傞偲丄倷乫亖俁倶2亄俀倎倶丂偐傜丄愙慄偺曽掱幃偼丄
丂倷亖乮俁倲2亄俀倎倲乯乮倶亅倲乯亄倲3亄倎倲2亄倐亖乮俁倲2亄俀倎倲乯倶亅俀倲3亅倎倲2亄倐
尨揰傪捠傞偙偲偐傜丄丂俀倲3亄倎倲2亅倐亖侽丂偡側傢偪丄丂俀倲3亄倎倲2亖倐丂丒丒丒丂(*)
愙慄偑俁杮堷偗傞偙偲偐傜丄(*)偼丄俁屄偺幚悢夝傪帩偮丅
丂倷亖俀倲3亄倎倲2丂偲偍偔偲丄丂倷乫亖俇倲2亄俀倎倲亖俇倲乮倲亄乮倎/俁乯乯亖侽丂傛傝丄丂倲亖侽丄亅倎/俁
倎亖侽丂偲偡傞偲丄俀倲3亄倎倲2亖倐丂偼幚悢夝傪侾屄偟偐帩偨側偄偺偱晄揔丅
倎亜侽丂偺偲偒丄嬌戝抣丂倎3/俀俈丂嬌彫抣丂侽丂偐傜丄(*)偑丄俁屄偺幚悢夝傪帩偮偨傔偵偼丄
丂侽亙倐亙倎3/俀俈
倎亙侽丂偺偲偒丄嬌戝抣丂侽丂嬌彫抣丂倎3/俀俈丂偐傜丄(*)偑丄俁屄偺幚悢夝傪帩偮偨傔偵偼丄
丂倎3/俀俈亙倐亙侽
偟偨偑偭偰丄媮傔傞揰乮倎丆倐乯偺懚嵼偡傞斖埻偼壓恾偺墿怓偄晹暘偱偁傞丅偨偩偟丄嫬奅慄偼
娷傑側偄丅
丂丂
丂忋婰栤戣偺椶戣偑丄搶杒戝妛丂棟丒岺乮侾俋俋俀乯偱弌戣偝傟偰偄傞丅
戞俇栤丂丂倶 偵偮偄偰偺俁師曽掱幃 俀倶3亅俁乮倎亄倐乯倶2亄俇倎倐倶亅俀倎2倐亖侽 偑俁偮偺憡堎側
丂丂傞幚悢夝傪帩偮偲偡傞丅偙偺偲偒丄揰乮倎丆倐乯偺懚嵼偡傞斖埻傪媮傔丄偦傟傪恾帵偣傛丅
乮夝乯丂倷亖俀倶3亅俁乮倎亄倐乯倶2亄俇倎倐倶亅俀倎2倐丂偲偍偔偲丄
丂倷乫亖俇倶2亅俇乮倎亄倐乯倶亄俇倎倐亖俇乮倶亅倎乯乮倶亅倐乯亖侽丂偐傜丄丂倶亖倎丄倐
戣堄傪枮偨偡偨傔偵偼丄丂倎亗倐丂偱丄
乮嬌戝抣乯亊乮嬌彫抣乯亖乮亅倎3亄倎2倐乯乮亅倐3亄俁倎倐2亅俀倎2倐乯亖倎2倐乮倎亅倐乯2乮俀倎亅倐乯亙侽
丂偡側傢偪丄丂倎亗侽丂偐偮丂倎亗倐丂偐偮丂倐乮俀倎亅倐乯亙侽丂偑媮傔傞懚嵼斖埻偱偁傞丅
偙傟傜傪恾帵偟偰壓恾傪摼傞丅偨偩偟丄嫬奅慄偼娷傑側偄丅
丂丂
乮捛婰乯丂椷榓俈擭侾侽寧俀擔晅偗
栤戣丂丂摍幃 倶2亄乮倝亅俀乯倶亄俀倎倐亄乮倐/俀亅俀倎乯倝亖侽丂傪枮偨偡幚悢倎丄倐偑懚廧偡傞傛偆側丄
丂丂幚悢倶偺斖埻傪媮傔傛丅偨偩偟丄倝亖併乮亅侾乯偱偁傞丅
乮夝乯丂倶2亅俀倶亄俀倎倐亄倝丒乮倶亄倐/俀亅俀倎乯亖侽丂傛傝丄倎丄倐丄倶 偼幚悢側偺偱丄
丂倶2亅俀倶亄俀倎倐亖侽丂丄倶亄倐/俀亅俀倎亖侽
戞俀幃偐傜丄丂倐亖係倎亅俀倶 傪戞侾幃偵戙擖偟偰丄丂倶2亅俀倶亄俀倎乮係倎亅俀倶乯亖侽
偡側傢偪丄丂俉倎2亅係倶倎亄倶2亅俀倶亖侽
丂倎 偺俀師曽掱幃偲傒偰丄幚悢夝傪帩偮偙偲偐傜丄敾暿幃傪俢偲偟偰丄
丂俢/係亖係倶2亅俉倶2亄侾俇倶亖亅係倶2亄侾俇倶亞侽丂偡側傢偪丄丂倶2亅係倶亝侽
偙傟傪夝偄偰丄丂侽亝倶亝係丂丂乮廔乯
乮捛婰乯丂椷榓俈擭侾侾寧侾俈擔晅偗
丂師偺搶杒戝妛丂屻婜棟宯乮俀侽侽俀乯偺栤戣偼丄嬌彫抣偺屄悢傪栤偆栤戣偱偁傞丅
栤戣丂丂 倎 偼幚悢偲偡傞丅娭悢 俥乮倶乯亖俀倶2倢倧倗倶亅倶2亅倎倶乮倶亅俀乯丂偺 倶亜侾 偵偍偗傞嬌彫
丂丂抣偺屄悢傪媮傔傛丅偨偩偟丄倢倧倗偼帺慠懳悢偲偡傞丅
乮夝乯丂俥乫乮倶乯亖俀乮俀倶倢倧倗倶亄倶乯亅俀倶亅俀倎乮倶亅侾乯亖係倶倢倧倗倶亅俀倎乮倶亅侾乯
丂俥乮倶乯偺 倶亜侾 偵偍偗傞嬌彫抣偺屄悢傪挷傋傞偵偼丄俥乫乮倶乯偺晞崋偺曄壔傪挷傋傟偽傛偄丅
偦偙偱丄丂俥乭乮倶乯亖係乮倢倧倗倶亄侾乯亅俀倎亖俀乮俀倢倧倗倶亄俀亅倎乯亖侽丂偲偍偔偲丄倷亖俀倢倧倗倶亄俀丂偼丄
倶亜侾丂偱丄倷偼扨挷憹壛偱丄倷亜俀丂偱偁傞偺偱丄
丂倎亜俀丂偺偲偒丄俀倢倧倗倶亄俀亅倎亖侽丂偲側傞 倶 偱丄俥乫乮倶乯偺晞崋偼晧偐傜惓偵曄傢傞偺偱丄
俥乮倶乯偼嬌彫偲側傞丅
丂倎亝俀丂偺偲偒丄俥乭乮倶乯亞侽丂偱丄俥乫乮倶乯偼扨挷憹壛偱丄俥乫乮侾乯亖侽丂偐傜丄俥乫乮倶乯亜侽丂偱丄
晞崋偺曄壔偼側偄偐傜丄嬌彫抣偼側偄丅
丂埲忋偐傜丄倎亜俀丂偺偲偒丄嬌彫抣偺屄悢偼丄侾屄偱丄
丂倎亝俀丂偺偲偒丄嬌彫抣偺屄悢偼丄侽屄偱偁傞丅丂丂乮廔乯
乮捛婰乯丂椷榓俈擭侾俀寧俀俀擔晅偗
丂師偺搶杒戝妛丂屻婜棟宯乮俀侽侽係乯偺栤戣偼丄夝偒曽偵岺晇傪梫偡傞栤戣偱偁傞丅
栤戣丂丂倶 偺曽掱幃 |倎丒倱倝値倶亄們倧倱俀倶|亖俀 偑夝傪傕偮傛偆側幚悢 倎 偺斖埻傪媮傔傛丅
乮夝乯丂忦審傛傝丄丂倎丒倱倝値倶亄們倧倱俀倶亖亇俀丂偱丄們倧倱俀倶亖侾亅俀倱倝値2倶丂傛傝丄
丂倎丒倱倝値倶亖俀倱倝値2倶亅侾亇俀
偙偙偱丄倱倝値倶亖侽丂偲偡傞偲丄幚悢夝偼懚嵼偟側偄偺偱丄倱倝値倶亗侽丂偲偟偰傛偄丅
乮侾乯丂倎丒倱倝値倶亖俀倱倝値2倶亅侾亄俀丂偡側傢偪丄丂倎亖俀倱倝値倶亄侾/倱倝値倶
丂倱倝値倶亖倲丂偲偍偔偲丄亅侾亝倲亝侾 偺斖埻偱丄倎亖俀倲亄侾/倲丂偑幚悢夝傪傕偮忦審傪挷傋傞丅
丂倷亖俀倲亄侾/倲丂偺僌儔僼偼丄
丂
丂倲亜侽丂偺偲偒丄丂俀倲亄侾/倲亞俀 丂丄倲亙侽丂偺偲偒丄丂俀倲亄侾/倲亝亅俀
丂丄倲亙侽丂偺偲偒丄丂俀倲亄侾/倲亝亅俀 丂側偺偱丄
丂側偺偱丄
亅侾亝倲亝侾 偺斖埻偱丄倎亖俀倲亄侾/倲丂偑幚悢夝傪傕偮忦審偼丄丂倎亝亅俀 丂丄倎亞俀
丂丄倎亞俀
乮俀乯丂倎丒倱倝値倶亖俀倱倝値2倶亅侾亅俀丂偡側傢偪丄丂倎亖俀倱倝値倶亅俁/倱倝値倶
丂倱倝値倶亖倲丂偲偍偔偲丄亅侾亝倲亝侾 偺斖埻偱丄倎亖俀倲亅俁/倲丂偑幚悢夝傪傕偮忦審傪挷傋傞丅
丂倷亖俀倲亅俁/倲丂偺僌儔僼偼丄
丂丂
丂倲亖亅侾丂偺偲偒丄倷亖侾丂丄倲亖侾丂偺偲偒丄倷亖亅侾丂側偺偱丄亅侾亝倲亝侾 偺斖埻偱丄
倎亖俀倲亅俁/倲丂偑幚悢夝傪傕偮忦審偼丄丂倎亝亅侾丂丄倎亞侾丂丂乮廔乯
丂丂丂埲壓丄岺帠拞