
2次方程式の理論で、「解の分離」という問題がある。「2つの解がともに正」とか「2つの
解がともに負」、「2つの解は異符号」、「2つの解はともに3より大きい」「1つの解は2より
大きく、残りの解は−1より小さい」 ・・・ など、いろいろとバリエーションが考えられる。
これまで、「解の分離」問題は解の存在範囲を確定するための問題という意識しかなく、
そのさらなる応用には、あまり関心を払わずにいた。この「解の分離」問題のうち、「解(ま
たは解の実数部)がともに負」という場合が力学系、制御系の安定性の判別に利用される
ことを最近知り、とても興味を持った。
このページでは、「解の分離」問題とその応用についてまとめようと思う。
例1 1次方程式 x+a=0 の解が負であるための必要十分条件は、 a>0 である。
例2 2次方程式 x2+ax+b=0 の解(または解の実数部)がともに負であるための必
要十分条件は、
a>0 かつ b>0
である。
実際に、判別式 D=a2−4b≧0 のときは、−a/2<0 、b>0 より、a>0、b>0
D=a2−4b<0 のときは、解の実数部=−a/2<0 より、a>0 で、また、
4b>a2>0 より、b>0
逆に、 a>0 かつ b>0 のとき、解(または解の実数部)はともに負になる。
例3 3次方程式の解がともに負の場合を考える。例えば、「−1、−2、−3」を解に持つ
3次方程式は、
(x+1)(x+2)(x+3)=0 より、 x3+6x2+11x+6=0
となる。
例1、例2を踏まえて、例3の具体的な場合から、
3次方程式 x3+ax2+bx+c=0 の解(または解の実数部)がともに負であるため
の必要十分条件は、
a>0 かつ b>0 かつ c>0
であることが予想される。
しかしながら、この予想は正しくない。
実際に、例えば、3次方程式 x3+x2+x+1=0 の解は、−1、±i で、解(または解の
実数部)がともに負になることはない。
しかしながら、上記の条件は解(または解の実数部)がともに負であるための必要条件
となり得る。すなわち、係数に負のものがあれば、その3次方程式は、解(または解の実
数部)がともに負であるとは言えない。
必要条件であることは、次のフルヴィッツの定理(Hurwitz’sTheorem)から分
かる。
フルヴィッツの定理(Hurwitz’sTheorem)
n次方程式 xn+a1xn-1+a2xn-2+・・・+an-2x2+an-1x+an=0 の解(または
解の実数部)がともに負であるための必要十分条件は、 Dk>0 (k=1、2、・・・、n)
である。
ここで、Dk は、n次方程式の係数から作られる次の行列
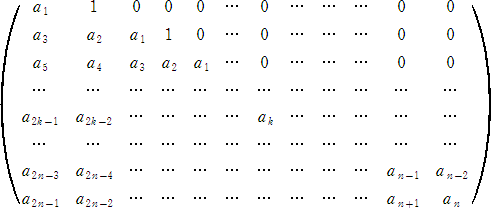
の左上隅からk行k列までをとって作った小行列式である。
(ただし、上記の行列において、 am=0 (m>n) とするものとする。)
この定理によれば、
3次方程式 x3+ax2+bx+c=0 の解(または解の実数部)がともに負であるた
めの必要十分条件は、
D1=a>0 、 D2=ab−c>0 、 D3=abc−c2>0
となる。
このとき、「a>0 かつ b>0 かつ c>0」が、必要条件であることは次のように示され
る。
D3=abc−c2=(ab−c)c>0 で、D2=ab−c>0 より、 c>0
このとき、 D2=ab−c>0 より ab>c>0 で、D1=a>0 なので、b>0
よって、 a>0 かつ b>0 かつ c>0 が成り立つ。
ところで、冒頭で述べた「制御系の安定性の判別に利用される」ことについて少し概観し
てみよう。私自身、制御系のことを専門的に学んだことがないので、もしかしたら舌足らず
の説明にしかならないかもしれない。そこはご容赦願いたい。
制御系の理論は、工学部の電気工学科や機械工学科の2年次位で学ぶようだ。ラプラ
ス変換や逆ラプラス変換の応用にもなっていると思う。
入力から出力に至る制御系において、瞬時的な外乱を与えて時間の経過とともに制御
系が再び平衡状態に落ち着くとき、その制御系は安定であるという。
ここで、入力と出力のラプラス変換(初期値は0)の比として、伝達関数が定義され、その
特性方程式の解を、s1、s2、・・・、sn とすると、伝達関数のインパルス応答は、eskt の
線形結合で表される。
したがって、解 s1、s2、・・・、sn の中に一つでも正のものがあると、時間 t → ∞ に対
して、その項は無限大に発散し、インパルス応答は、0 にならない。
よって、制御系が安定であるためには、特性方程式の解は全て負でなければならない。
(コメント) 理論の詳細は浅学の身で不確かであるが、フルヴィッツの定理がどのような
意味を持っているのか、分かったような気分にさせてくれた。
制御系の理論を学んだ方で高校生でも分かるように説明していただける方は
いらっしゃらないだろうか?是非メールをお願いします。
(追記) 平成26年10月13日付け
冒頭の例2において、2次方程式 x2+ax+b=0 の解(または解の実数部)がともに
負であるための必要十分条件は、a>0 かつ b>0 であることを見た。
2つの実数解を α、β とすれば、解と係数の関係より、 α+β=−a、αβ=b なので、
このことは、
a>0 、 b>0 ならば、 α<0 、β<0
であり、逆もまた成り立つと言うことである。
α<0、β<0 ならば、 a=−(α+β)>0、b=αβ>0 は至極当然であるし、α、β
が実数ならば、αβ=b>0 から α、βが同符号が分かり、α+β=−a<0 から、
α<0、β<0 も当然の帰結であろう。
このように2つの解について明白なことも、3つの解ではどう?と問われてしまうと一瞬たじ
ろいでしまう。
昭和49年度の学習院大学経済学部の入試問題に次のような問題が出題されている。
α、β、γ を実数とするとき、 α+β+γ>0、αβ+βγ+γα>0、αβγ>0
ならば、α>0、β>0、γ>0 であることを証明せよ。
α>0、β>0、γ>0 ならば、α+β+γ>0、αβ+βγ+γα>0、αβγ>0 で
あることは自明だろう。問題は、この逆も成り立つことを証明せよと我々に問うている。
2つの解の場合とは違って、この3つの解の場合を示すことはそう単純にはいかないだろう。
(証明) αβγ>0 から、 α、β、γの何れも正 または 正が1つと負が2つ
正が1つと負が2つの場合、一般性を失うことなく α>0、β<0、γ<0 としてよい。
このとき、 α>α+β>α+β+γ>0、α>α+γ>α+β+γ>0 より、
α2>(α+β)(α+γ)=α2+αβ+βγ+γα なので、αβ+βγ+γα<0
これは、αβ+βγ+γα>0 に矛盾するので、正が1つと負が2つの場合は起こらな
い。
よって、 α>0、β>0、γ>0 が成り立つ。 (証終)
上記のような手法で示すことはできたが、この解法では、「4つの解」、「5つの解」、・・・ に
対応できるとは考えにくい。実は、このような問題に対して、「魔法の道具」が存在する。
(別証) 実数 x の関数 F(x)=(x−α)(x−β)(x−γ) を考える。
F(x)=x3−(α+β+γ)x2+(αβ+βγ+γα)x−αβγ
条件より、 −(α+β+γ)<0 、 αβ+βγ+γα>0 、−αβγ<0
したがって、 x≦0 において、 F(x)<0 が成り立つ。
このことは、 F(x)=0 ならば、 x>0 であることを示す。
F(α)=F(β)=F(γ)=0 なので、 α>0、β>0、γ>0 が成り立つ。 (別証終)
(コメント) 何となく狐につままれたような...そんな雰囲気!
この「魔法の道具」の効用を実感するのは、例えば、次のような問題においてだろう。
平成12年度の学習院大学理学部の入試問題
実数α、β、γが、α<β<γ、α+β+γ=0、αβ+βγ+γα=−3 を満たす
とき、不等式 −2<α<−1<β<1<γ<2 が成り立つことを示せ。
(解) 実数 x の関数 F(x)=(x−α)(x−β)(x−γ) を考える。
F(x)=x3−(α+β+γ)x2+(αβ+βγ+γα)x−αβγ
条件を代入して、 F(x)=x3−3x−p (p=αβγとおく)
F’(x)=3x2−3=3(x+1)(x−1)=0 とおくと、 x=1、−1
F”(x)=6x より、 F”(1)=6>0 、F”(−1)=−6<0 なので、
F(x)は、x=1で極小値F(1)=−2−p、x=−1で極大で極大値F(−1)=2−p である。
F(x)=0 は、3つの実数解をもつので、 F(1)=−2−p<0 、F(−1)=2−p>0
すなわち、 −2<p<2 でなければならない。
このとき、 F(−2)=−2−p<0 、F(−1)=2−p>0
F(1)=−2−p<0 、F(2)=2−p>0
なので、中間値の定理により、 −2<α<−1<β<1<γ<2 が成り立つ。 (終)
(コメント) 条件式を変形して示すことは、ほとんど不可能だろう。
...と思っていたところ、DD++さんからコメントを頂きました。(平成26年10月16日付け)
ところが、不等式証明には案外いろんな手段があるもので、自分が試験を解く立場なら直
接変形の方針はあまりとりたくありませんし、そもそも解と係数の関係と中間値の定理使う方
が先に思いつくでしょうけど...。
本題から確実に脱線してますが、以下高校数学 IIB 範囲での直接変形での解法です。
(別解) α+β+γ = 0 より、 α+γ = -β ......(1)
αβ+βγ+γα = (α+γ)β+γα = -β2+γα = -3 より αγ = β2-3 ......(2)
(1) と (2) を用いると、(α-γ)2 = (α+γ)2-4αγ = β2-4(β2-3) = 12-3β2 より、
α-γ = -√(12-3β2) ......(3) (∵ α-γ は負の実数)
(1) と (3) を加減することにより、 2α = -β-√(12-3β2) 、2γ = -β+√(12-3β2)
を得る。
ここで、α < β < γ であったから、-β-√(12-3β2) < 2β < -β+√(12-3β2) を変形
して、 |3β| < √(12-3β2)
両辺とも正なので平方して、9β2 < 12-3β2 より、 -1 < β < 1
ここで、 β = 2sinθ ( -π/6 < θ < π/6 ) とおくと、
2α = -2sinθ-2
となり、 π/6 < θ+π/3 < π/2 より、 -4 < 2α < -2 すなわち、 -2 < α < -1
-π/2 < θ-π/3 < -π/6 より、 2 < 2γ < 4 すなわち、 1 < γ < 2
以上より、 -2 < α < -1 < β < 1 < γ < 2
(コメント) 直接変形でも示せるんですね!DD++さんに感謝します。
次の「平成4年 学習院大学法学部 入試問題」も「魔法の道具」が活躍する。
0以上の実数α、β、γが次の条件 α+β+γ=10 、αβ+βγ+γα=25
を満たすとき、αβγの取り得る値の範囲を求めよ。
(解) 実数 x の関数 F(x)=(x−α)(x−β)(x−γ) を考える。
F(x)=x3−(α+β+γ)x2+(αβ+βγ+γα)x−αβγ
条件を代入して、 F(x)=x3−10x2+25x−p (p=αβγとおく)
F’(x)=3x2−20x+25=(3x−5)(x−5)=0 とおくと、 x=5/3、5
α、β、γが正または0の実数となるためには、
F(0)=−p≦0 、F(5/3)≧0 、F(5)=−p≦0
ところで、 F(5/3)=125/27−250/9+125/3−p=500/27−p なので、
求める範囲は、 0≦p≦500/27 (終)
以下、工事中