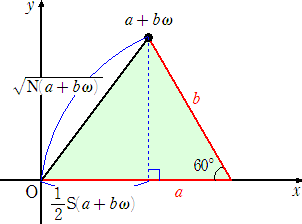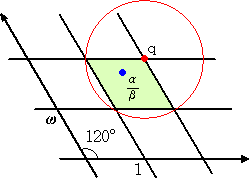3.2次体の整数 
平成17年の私自身の積み残しの問題として、
y3=x2−1 を満たす自然数解は、(x,y)=(3,2) のみ
というものがある。この問題は、平成17年6月2日にHN「通り人」さんが出題されたもので
ある。これに対して、当HPがいつもお世話になっているHN「らすかる」さんが、「Thue方程
式」の問題に翻訳して、プログラムにより解決された。(平成17年6月5日付け)
右辺を因数分解すると、 y3=(x+1)(x−1) である。連続する正の奇数の積は三乗数
にならないので、xは奇数に限る。
xが奇数(x≧3)、yが偶数(y≧2)なので、 x=2m+1、y=2n (m、n≧1)
とおくと、 4m(m+1)=8n3 となり、 m(m+1)=2n3
mが偶数のとき、 m=2k (k≧1)とおくと、 k(2k+1)=n3
k と 2k+1 は互いに素なので、両方とも三乗数でなければならない。
そこで、 k=t3(t≧1)、2k+1=s3 (s≧1)とおくと、 2t3+1=s3
となる。
同様にして、
mが奇数のとき、 m=2k−1 (k≧1)とおくと、 k(2k−1)=n3
k と 2k−1 は互いに素なので、両方とも三乗数でなければならない。
そこで、 k=t3(t≧1)、2k−1=s3 (s≧1)とおくと、 2t3−1=s3
となる。
したがって、2t3±1=s3 (Thue方程式)を解けば良いことになる。
このとき、 pari/gp というプログラムで
th=thueinit(x^3-2)
thue(th,1)
thue(th,-1)
と入力するだけで、(s,t)=±(1,0),±(1,1)という全解が得られる。
問題の条件より、(s,t)=(1,1) で、このとき、 k=1
よって、m=n=1 となり、自然数解は (x,y)=(3,2) のみ。
らすかるさんによれば、「手計算で簡単に解けるような問題ではない」ということである。
北海道大学の中村先生に、この問題について伺ったところ、らすかるさんと同じく、「簡
単な計算ではできない」とのことである。
y3=x2−1 を y3+1=x2 と変形し、1の3乗根ωを用いて、(y+1)(y+ω)(y+ω2)=x2
と因数分解。このとき、Q(ω)での素数の分解法則やZ[ω]の単項イデアル整域という性質
を用いて証明できるだろう
との助言を頂いた。
このページでは、中村先生からの指針を参考にしながら、冒頭の問題解決のための理
論的な知識を整理していきたいと思う。
表題の「2次体」の「体」は、数学における「群・環・体」の「体」のことである。これは、あま
り難しく考える必要はなく、我々が通常計算している世界が、「体」の世界である。簡単に言
えば、「体」とは、四則演算が自由にできる数の集合のことを言う。
例(有理数体 Q) 有理数の集合で、演算(+−×÷)が可能である。
例(実数体 R) 実数の集合で、演算(+−×÷)が可能である。(→中学で学習)
例(複素数体 C) 複素数の集合で、演算(+−×÷)が可能である。(→高校で学習)
上記の3つの数体には、 Q ⊂ R ⊂ C という関係がある。
このような関係があるとき、Q は R の部分体、R は C の部分体であるという。
整数論の基礎知識 において、ガウスの整数のいろいろな性質を考察した。
(ガウスの整数) a+b・i (a、b は有理整数 、i は虚数単位)
この整数は、和・差・積の演算について閉じているが、商については閉じていない。
したがって、ガウスの整数の集合は、体にはならない。
そこで、i を虚数単位として、複素数 a+b・i (a、b は有理数)の集合を考える。
この集合は、通常 Q(i) で表される。
ここでは四則演算が自由にできるので体となる。 Q(i) をガウスの数体と言う。
Q(i) は、虚2次体である。これに対して、Q( )などは実2次体と言われる。
)などは実2次体と言われる。
α=a+b・i を解に持つ2次方程式は、
(X−α)(X− )=X2−(α+
)=X2−(α+ )X+α・
)X+α・ =0
=0
で与えられる。 このとき、係数はすべて有理数である。
多項式 (X−α)(X− ) のことを、 α の主多項式という。
) のことを、 α の主多項式という。
さて、冒頭の問題解決のためには、まず、虚2次体 Q(ω) について、その性質を調べる
必要がありそうだ。
ω は、1の3乗根で、2次方程式 X2+X+1=0 の解である。解の公式から、
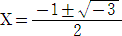
である。
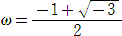
とおくと、
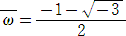
である。
明らかに、 ω+ =−1 、 ω・
=−1 、 ω・ =1 が成り立つ。
=1 が成り立つ。
また、 ω2+ω+1=0 であることから、  =ω2 である。
=ω2 である。
a+b (a、b は有理数)の集合からなる体を考えるので、通常は、Q(
(a、b は有理数)の集合からなる体を考えるので、通常は、Q( )とす
)とす
るところだが、実は、Q(ω) を用いる理由がある。
Q( )における整数は、実は、
)における整数は、実は、
a+b・ω (a、b は有理整数)
の形に限定されるらしい。そういうこともあって、Q(ω) を用いることが納得される。
α=a+b・ω (a、b は有理数)に対して、その共役を  =a+b・
=a+b・ と定義する。
と定義する。
このとき、α=a+b・ω のノルム(Norm)を
N(a+b・ω)=(a+b・ω)・(a+b・ )=a2−ab+b2
)=a2−ab+b2
と定義する。明らかに、ノルムの値は、0 以上の有理数である。
ノルムについて、次の性質が成り立つ。(証明は、明らかだろう。)
N(α・β)=N(α)・N(β) 、 N(α/β)=N(α)/N(β)
ノルムと同様にして、シュプール(Spur)(または、トレース(trace))が定義される。
S(a+b・ω)=(a+b・ω)+(a+b・ )=2a−b
)=2a−b
シュプールについて、次の性質が成り立つ。(証明は、明らかだろう。)
S(α+β)=S(α)+S(β)
明らかに、シュプールの値は、0 以上の有理数である。
例 α=5+8ω のノルム N(α)=52−5・8+82=25−40+64=49
シュプール S(α)=2・5−8=10−8=2
α=a+b・ω に対して、そのノルムとシュプールは、どんな幾何学的意味があるのだろう
か?下図を、ボーっと眺めていると、その意味がよく分かる。
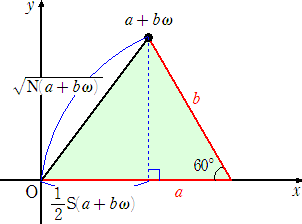
N(a+b・ω)は、2辺の長さが a、b で、その間の角が60°の三角形で、その角の対辺
の長さの平方である。
S(a+b・ω)は、2辺の長さが a、b で、その間の角が60°の三角形で、第3辺のa方向
の正射影の長さの2倍である。
Q(ω) において、 a+b・ω (a、b は有理整数) の形の数を「整数」と定義する。
全ての整数の約数となる整数を、単数という。単数は、有理整数 1 と同じ働きを持つ。
Q( i ) において、単数は、 1 、−1 、 i 、 −i の4個であった。それでは、Q(ω)
に
おいて、単数とは、どのようなものであろうか。実際に、求めてみよう。
単数の性質から、 N(a+b・ω)=1 が成り立つので、 a2−ab+b2=1
a の2次方程式 a2−ab+b2−1=0 において実数解を持つので、判別式をDとすると、
D=b2−4(b2−1)=4−3b2≧0 となる。 b は整数なので、 b=0、1、−1
b=0 のとき、 a2=1 より、 a=1、−1
b=1 のとき、 a2−a=0 より、 a=0、1
b=−1 のとき、 a2+a=0 より、 a=0、−1
従って、求める単数は、次の6個である。
1 、−1 、ω 、−ω 、 1+ω 、−1−ω
ここで、 1+ω=−ω2 なので、単数として、
1 、−1 、ω 、−ω 、 ω2 、−ω2
としてもよい。また、次の性質も面白い。
Q(ω) において、整数のノルムは、3以上である。
したがって、ノルムが2となる整数は存在しない。
実際に、もし存在したとすると、a2−ab+b2=2 であるが、判別式をDとすると、
D=b2−4(b2−2)=8−3b2≧0 となる。 b は整数なので、 b=0、±1、±2
b=0 のとき、 a2=2 より、 a は整数とならない。
b=1 のとき、 a2−a−1=0 より、 a は整数とならない。
b=−1 のとき、 a2+a−1=0 より、 a は整数とならない。
b=2 のとき、 a2−2a+2=0 より、 a は整数とならない。
b=−2 のとき、 a2+2a+2=0 より、 a は整数とならない。
以上から、a2−ab+b2=2 を満たす整数解は存在しない。
整数 α に対して、単数および、 α に単数を乗じたものは、自明な約数で、有理整数にお
ける、1と−1 と同様に因数としては、度外視して考えるものとする。
例 6=1・6 とは普通考えない。 6=2・3 と因数に分解する方が自然であろう。
整数 α に対して、自明でない約数を、真の約数という。
このとき、整数 α が、0 でも単数でもなく、かつ、真の約数を持たないとき、素数であると
いう。
例 Q(ω) において、 1+2ω= は素数である。
は素数である。
実際に、N(1+2ω)=3 で、整数のノルムは3以上であるから、1+2ω は真の約数
を持ち得ない。
このことから、3 は、Q(ω) において素数でないことも分かる。
整数 α に対して、素数 p 、q 、・・・ があって、 α=p×q×・・・ と積の形にかけるとき、
整数 α は、素因数に分解されるという。
これまでの話から、整数 α が有限個の素因数に必ず分解できるということは理解できる
だろう。しかし、素因数分解において、大切なことは、その分解の一意性にある。もし、一意
性が成立すれば、有理整数における性質が、Q(ω) の整数においても同様に成り立つこと
になる。
Q(ω) においても、素因数分解の一意性が成り立つ。
このことを確認するには、まず次の定理(整除の定理)が必要だ。
定理 任意の整数 α 、β (β≠0) に対して、
α = β・q+r ( N(r)<N(β) )
を満たす整数 q 、r が存在する。
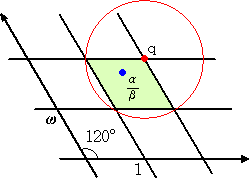 |
(証明) ガウス平面(複素数平面)において、明らか
に、ある整数 q が存在して、N(α/β−q)<1
とできる。そこで、 r=α−β・q とおくと、r は
整数で、
N(r)=N(α−β・q)=N(β・(α/β−q))
=N(β)・N(α/β−q)<N(β)
以上から、 α = β・q+r ( N(r)<N(β) ) を
満たす整数 q 、r が存在する。(証終) |
この定理により、Q(ω) の整数においても、ユークリッドの互除法を行うことができる。
従って、ガウスの整数と同様の議論により、Q(ω) においても素因数分解の一意性が成
り立つ。
さて、上記の例で、「 Q(ω) において、整数 1+2ω= は素数である」ことを述べ
は素数である」ことを述べ
た。それでは、 Q(ω) における素数として他にどんなものがあるのだろうか?
いま、整数 α を素数として、 α で割り切れる正の有理整数のうちで最小のものを、p と
する。このような p は必ず存在する。(例えば、N(α)は、α で割り切れる。)
このとき、 p は、有理素数である。
実際に、 α は素数で単数ではないから、p ≧ 3 で、p が有理素数でないとすると、
p = x・y ( p>x>1 、p>y>1 )
となる有理整数 x 、y が存在し、x または y は、α で割り切れる。
これは、p の最小性に矛盾する。 よって、 p は、有理素数である。
したがって、素数 α は、有理素数 p の約数となる。そこで、 p = α・β とおける。
このとき、 N(p)=N(α)・N(β) で、N(p)=p2 なので、
N(α)=p または N(α)=p2
となる。
N(α)=p のとき、 p=α・ で、これは、p の素因数分解となるので、有理素数 p は
で、これは、p の素因数分解となるので、有理素数 p は
Q(ω) における素数とはなり得ない。 (例 3=(1+2ω)(1+2 ) )
) )
N(α)=p2 のとき、 N(β)=1 で、β は単数で、α は、p と同伴数となる。
このとき、p は、Q(ω) においても素数となる。
したがって、有理素数 p を与えたとき、
a2−ab+b2=p が有理整数解 a、b を持てば、 α=a+b・ω は素数
a2−ab+b2=p が有理整数解 a、b を持たなければ、 p そのものが素数
であることが分かった。
例 有理素数の 3 は、Q(ω) においては素数となりえない。
実際に、 a2−ab+b2=3 において有理整数解 a、b が存在するとすれば、
判別式 D =b2−4(b2−3)=12−3b2≧0 より、 b=0、±1、±2
b=0 のとき、 a2=3 となり、 a は整数とならない。
b=1 のとき、 a2−a−2=0 となり、 (a−2)(a+1)=0 より、 a=2、−1
よって、 2+ω 、−1+ω は、素数である。
b=−1 のとき、 a2+a−2=0 となり、 (a+2)(a−1)=0 より、 a=−2、1
よって、 −2−ω 、1−ω は、素数である。
b=2 のとき、 a2−2a+1=0 となり、 (a−1)2=0 より、 a=1
よって、 1+2ω は、素数である。
b=−2 のとき、 a2+2a+1=0 となり、 (a+1)2=0 より、 a=−1
よって、 −1−2ω は、素数である。
以上から、a2−ab+b2=3 は、有理整数解 a、b をもつので、有理素数の 3 は、Q(ω)
においては素数となりえない。
この6個の素数(2+ω、−1+ω、−2−ω、1−ω、1+2ω、−1−2ω)は互いに同伴数
である。
実際に、1+ω=−ω2、ω3=1 で、単数 1、−1、ω、−ω、1+ω、−1−ω を用いて、
−1+ω=(2+ω)ω 、−2−ω=(2+ω)(−1) 、1−ω=(2+ω)(−ω)
1+2ω=(2+ω)(1+ω) 、−1−2ω=(2+ω)(−1−ω)
と書けることから明らかであろう。
例 有理素数の 5 は、Q(ω) においても素数である。
実際に、 a2−ab+b2=5 において有理整数解 a、b が存在するとすれば、
判別式 D =b2−4(b2−5)=20−3b2≧0 より、 b=0、±1、±2
b=0 のとき、 a2=5 となり、 a は有理整数とならない。これは、矛盾。
b=±1 のとき、 a2−(±1)a−4=0 となり、 a は有理整数とならない。これは、矛盾。
b=±2 のとき、 a2−(±2)a−1=0 となり、 a は有理整数とならない。これは、矛盾。
以上から、a2−ab+b2=5 は、有理整数解 a、b をもたないので、有理素数の 5 は、
Q(ω) においても素数となる。
実は、有理素数 p が、Q(ω) において、素数になるかどうかについては、次の定理が知ら
れている。
定理 2次体 Q(ω) において、有理素数 p は、
p ≡ 1 (mod 3) のとき、 素数にならない
p ≡ 2 (mod 3) のとき、 素数になる
この定理によれば、有理素数の5は素数で、7は素数にはならないことが分かる。そして、
±(3+ω)、±(−2+ω)、±(3+2ω)、±(−1+2ω)、±(1+3ω)、±(2+3ω)
が互いに同伴な素数であることも分かる。
さて、Legendre の記号 (a/p) を用いて、上記の定理を証明してみよう。
(証明) a2−ab+b2=p を満たす有理整数解 a、b が存在するとする。
このとき、 4p=4a2−4ab+4b2=(2a−b)2+3b2 と書ける。
よって、 (2a−b)2≡p (mod 3) なので、 (p/3)=1 となる。
Euler の規準より、 (p/3)≡p (mod 3) なので、 p≡1 (mod 3) となる。
逆に、 p≡1 (mod 3) とする。このとき、明らかに、(p/3)=1 である。
平方剰余の相互法則より、 (p/3)(3/p)=(−1)(p−1)/2・(3−1)/2=(−1)(p−1)/2
なので、 (3/p)=(−1)(p−1)/2 である。
よって、 p は奇素数なので、
(−3/p)=(−1/p)(−3/p)=(−1)(p−1)/2・(−1)(p−1)/2=(−1)(p−1)=1
すなわち、 方程式 X2≡−3 (mod p) は有理整数解 m を持つ。
このとき、 p と m− の最大公約数を M とすると、
の最大公約数を M とすると、
M= 1 または M= p または M= α ( p=α・ )
)
の何れかになるが、m− は、p で割り切れないので、M= p は起こりえない。
は、p で割り切れないので、M= p は起こりえない。
また、M= 1 とすると、 p は、 m− 、m+
、m+ と互いに素になる。
と互いに素になる。
すなわち、 (m− )(m+
)(m+ )=m2+3 と p は互いに素となる。
)=m2+3 と p は互いに素となる。
これは、m2≡−3 (mod p) に矛盾する。
よって、 M= α ( p=α・ ) の場合しか起こらない。
) の場合しか起こらない。
以上から、 a2−ab+b2=p を満たす有理整数解 a、b が存在する。(証終)
(コメント) 厳密な証明は難しいので、雰囲気を味わうだけ...。
以上で、2次体(虚2次体) Q(i)、Q(ω) のもつ性質をいろいろ見てきた。これらは何れ
も単数の個数は有限で、かつ、素因数分解の一意性が有理整数同様保たれている。
しかし、2次体の中には、単数が無限個あったり、素因数分解の一意性が成り立たないも
のもある。
単数が無限個ある2次体の例 ・・・・・ Q( )
)
素因数分解の一意性が成り立たない2次体の例 ・・・・・ Q( )
)
一般論に入る前に、それらの2次体の構造を探訪することにしよう。
Q( )における整数は、 α = a+b
)における整数は、 α = a+b (a、b は有理整数)の形をしている。
(a、b は有理整数)の形をしている。
α = a+b に対して、その共役は、
に対して、その共役は、 = a−b
= a−b である。
である。
このとき、 α のノルム N(α)=α・ =a2−2b2
=a2−2b2
シュプール S(α)=α+ =2a
=2a
である。
例 α = 1+ について、N(α)、S(α)を求めてみよう。
について、N(α)、S(α)を求めてみよう。
N(α)=(1+ )(1−
)(1− )=1−2=−1
)=1−2=−1
S(α)=1+ +1−
+1− =2
=2
この例からも分かるように、Q( )の世界では、
)の世界では、
N(α)<0 、 N(α)≠|α|2
という場合も起こりうる。 これは、Q(i)、Q(ω) ではなかった性質である。
今、 α = a+b を単数とすると、α は、1の約数なので、1=α・α’ となる整数 α’が
を単数とすると、α は、1の約数なので、1=α・α’ となる整数 α’が
存在する。
よって、 N(1)=N(α・α’)=N(α)・N(α’) で、N(1)=1 より、 N(α)=1、−1
すなわち、 a2−2b2=1 、 a2−2b2=−1
これらを解くと、 ( a , b )=( ±1 , 0 )、( 1 , 1 )
このとき、 1 、 −1 、 1+ が単数となるが、 α’=1/α=−1+
が単数となるが、 α’=1/α=−1+ も単数である。
も単数である。
また、 1=α・α’ より、 1=αn・α’n なので、 αn も単数となる。
このことから、 Q( )において、単数は無限個あることが理解される。
)において、単数は無限個あることが理解される。
Q( )における整数は、 α = a+b
)における整数は、 α = a+b (a、b は有理整数)の形をしている。
(a、b は有理整数)の形をしている。
α = a+b に対して、その共役は、
に対して、その共役は、 = a−b
= a−b である。
である。
このとき、 α のノルム N(α)=α・ =a2+5b2
=a2+5b2
シュプール S(α)=α+ =2a
=2a
である。
今、 α = a+b を単数とすると、α は、1の約数なので、1=α・α’ となる整数 α’
を単数とすると、α は、1の約数なので、1=α・α’ となる整数 α’
が存在する。
よって、 N(1)=N(α・α’)=N(α)・N(α’) で、N(1)=1 より、 N(α)=1
すなわち、 a2+5b2=1
この解は、 ( a , b )=( ±1 , 0 ) のみである。
よって、 Q( )における単数は、 1 、 −1 の2つである。
)における単数は、 1 、 −1 の2つである。
一般に、Q(i)、Q(ω) 以外の虚2次体において、単数は、1 、 −1 の2つしか存在しな
いことが知られている。
Q( )において、素因数分解の一意性が成り立たないことは、次の例から明らかだ
)において、素因数分解の一意性が成り立たないことは、次の例から明らかだ
ろう。
例 6=2・3=(1+ )(1−
)(1− )
)
(コメント) これを書いていると、院試で整数論の土井先生から、「素因数分解の一意性が
成り立たない例をあげてください。」と質問されたことが突然思い出された。
H.Nakao さんからのコメントです。(令和3年10月2日付け)
可能であれば、整数環上で、"既約である"と"素である"とが一致しない具体例を挙げて
欲しいです。
Z(有理整数環)では、nが既約元であることとnが素元であることは同値です(良く知られてい
る)が、2Z(偶数の有理整数のみからなる環、単元を持たないことに注意)では、
6は2Zで既約元である。(6を2つの偶数の積に分解できないから)
6は2Zで素元ではない。(36=6*6=2*18より、6は36を割るが、6は2を割らない、かつ、6は
18を割らないから)
となることを、
Joseph. H. Silverman, "A Friendly Introduction to Number Theory Second
Edition",
Prentice Hall Inc., 2001, ISBN0-13-030954-0
を読んた時に、こんな簡単な例があったのかと、衝撃を受けました。これにより、"素"である
ことの重要さが分かりました。
以下、工事中