
F(X+Y)=F(X)+F(Y) などのように、未知関数 F(X) を含む方程式を関数方程式という。
関数方程式は、例えば、次のようにして構成される。
関数方程式 
F(X+Y)=F(X)+F(Y) などのように、未知関数 F(X) を含む方程式を関数方程式という。
関数方程式は、例えば、次のようにして構成される。
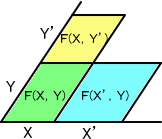 |
左図のように、2本の半直線が定角で交わっている。 辺の長さが、X、Yである平行四辺形の面積を F(X,Y) とおく。 このとき、面積の関係から、 F(X+X’,Y)=F(X,Y)+F(X’,Y) F(X,Y+Y’)=F(X,Y)+F(X,Y’) が成り立つ。 |
いま、Yを固定して、F(X,Y)=F(X) とおくと、第一式より、 F(X+X’)=F(X)+F(X’)
X’=Y とおけば、 F(X+Y)=F(X)+F(Y)
この関数方程式は、Cauchy の方程式といわれる。
関数方程式は、その関数の持っている性質を表している。したがって、関数方程式におけ
る興味の中心は、
その性質を満たす関数をすべて求めたい
ということである。
関数 F(X)について、連続性や微分可能性といった、ある意味で厳しい条件を設定すると、
定数の自由度を除いて、関数は一意に定まることが多い。
例 全ての実数 X、Y に対して、F(X+Y)=F(X)+F(Y)を満たす関数 F(X) について考えて
みよう。
まず、F(0+0)=F(0)+F(0) より、F(0)=0 である。
また、F(2)=F(1+1)=F(1)+F(1)=2F(1) 、同様にして、F(3)=3F(1) 、・・・
一般に、自然数 n に対して、F(n)=nF(1)
F(0)=F(X+(−X))=F(X)+F(−X)=0 より、F(−X)=−F(X)
よって、F(X)は奇関数である。
この性質から、全ての整数 n に対して、F(n)=nF(1)
また、F(1)=F(2・1/2)=2F(1/2) より、F(1/2)=(1/2)F(1) 、
同様にして、F(1/3)=(1/3)F(1)、・・・
一般に、自然数 n に対して、F(1/n)=(1/n)F(1)
同様にして、自然数 m、n に対して、 F(m/n)=mF(1/n)=(m/n)F(1)
よって、全ての正の有理数 r に対して、F(r)=rF(1) が成り立つ。
F(X)は奇関数であるので、全ての有理数 r に対して、F(r)=rF(1) が成り立つ。
ここで、関数 F(X) の連続性を仮定する。
関数 F(X) が連続とは、簡潔に言えば、グラフがつながっているということである。
厳密に連続の定義を述べようとすれば、次のようなε‐δ論法を用いる。
関数 F(X) が X=a で連続とは、
「任意の正数εに対して、ある正数δが存在して、
|X−a|<δならば、|F(X)−F(a)|<ε」
が成り立つときをいう。
全ての実数 aに対して連続であるとき、関数F(X)は連続であるという。
関数F(X)が連続であるとき、
「無理数Xに収束する有理数列 {Xn} に対して、数列 {F(Xn)} が F(X) に収束する」
この事実から、全ての実数 X、Y に対して、F(X+Y)=F(X)+F(Y)を満たす連続関数
F(X) は、
F(X)=XF(1) (Xは実数)
の形しかないことになる。
関数 F(X) の連続性のかわりに微分可能性を仮定すれば、もっと、より簡単に結果を
示すことができる。
| 関数F(X)が X=a で微分可能とは、 | が存在するときをいう。 |
全ての実数 a に対して微分可能であるとき、関数F(X)は微分可能であるという。
関数F(X)が微分可能であるとき、関数方程式 F(X+Y)=F(X)+F(Y) の両辺を Y で微分
して、
F’(X+Y)=F’(Y) (Xは定数と考える!)
ここで、Y=0 とおくと、 F’(X)=F’(0) より、 F(X)=XF’(0) となる。
また、X=1 を代入すれば、 F(1)=F’(0) である。
以上から、
全ての実数 X、Y に対して、F(X+Y)=F(X)+F(Y) を満たす微分可能な関数 F(X) は、
F(X)=XF(1) (Xは実数)
の形しかない。
(注意) 上記の計算で、関数 F(X) の連続性、微分可能性を全実数で仮定したが、Cauchy
の方程式が成り立つときは、実は、X=0での連続性、微分可能性を仮定すれば十分
である。次の定理が成り立つ。
定理 関数 F(X) が、関数方程式 F(X+Y)=F(X)+F(Y) を満たすとき
(1) 関数 F(X) が、X=0 で連続ならば、全ての実数で連続
(2) 関数 F(X) が、X=0 で微分可能ならば、全ての実数で微分可能
(証明)(1) 関数 F(X) が、X=0 で連続より、h→0 のとき、F(h)→F(0)=0 である。
よって、全ての実数Xに対して、h→0 のとき、F(X+h)=F(X)+F(h)→F(X) となり、連
続となる。
(2) 関数 F(X) が、X=0 で微分可能より、F’(0) が存在する。
このとき、F(X+h)−F(X)=F(h) なので、明らかに、全ての実数Xに対して、F’(X) が存在
し、微分可能となる。 (証終)
話題を、元の平行四辺形の面積 F (X,Y) に戻せば、上記の理論から、
F(X,Y)=F(X)=XF(1)=XF(1,Y)
と書けることになる。ただし、F(X,Y) は連続とする。
面積の関係式の第二式より、F(1,Y)もまた Cauchy の方程式をみたすので、
F(1,Y)=YF(1,1)
と書ける。
従って、辺の長さが、X、Yである平行四辺形の面積は、 F(X,Y)=XYF(1,1) と書ける
ことが分かった。
関数方程式は、Cauchy の方程式以外にも次のものがよく知られている。
(1) 全ての実数 X、Y に対して、F(X+Y)=F(X)F(Y)
(2) 全ての正数 X、Y に対して、F(XY)=F(X)+F(Y)
(3) 全ての正数 X、Y に対して、F(XY)=F(X)F(Y)
これらは全て、基本的に Cauchy の方程式に帰着される。
以下の議論で、定数関数は自明なので、除外して考えることにし、関数は全て連続とする。
(1) 全ての実数 X、Y に対して、F(X+Y)=F(X)F(Y)
この関数方程式を満たす関数 F(X) は、正値関数となる。すなわち、
全てのXに対して、F(X)>0
実際に、F(0)=F(0)F(0) より、F(0)=0、1 であるが、F(0)=0 とすると、
F(X)=F(X+0)=F(X)F(0)=0 となるので、F(0)=1 である。
いま、ある実数Xに対して、F(X)=0 と仮定すると、F(0)=F(X)F(−X)=0 となり矛盾。
従って、全ての実数に対して、F(X)≠0 となる。このとき、全ての実数に対して、
F(X)=F(X/2)2>0 が成り立つ。
よって、log F(X)=G(X) とおくと、G(X+Y)=G(X)+G(Y) で、Cauchy の方程式となる。
G(X)=XG(1) なので、A=G(1) とおくと、F(X)=eAX (Aは定数)となる。
(2) 全ての正数 X、Y に対して、F(XY)=F(X)+F(Y)
この関数方程式を満たす関数 F(X) は、X=0 で定義されない。
実際に、X=0 で定義されるものと仮定すると、F(0)=F(X)+F(0) より、F(X)=0 で矛盾。
X、Y は正数なので、X=eu、Y=ev とおける。そこで、G(u)=F(eu) とおくと、
G(u+v)=G(u)+G(v) で、Cauchy の方程式となる。
G(u)=uG(1) なので、G(1)=A とおくと、F(X)=Alog X (Aは定数)となる。
(3) 全ての正数 X、Y に対して、F(XY)=F(X)F(Y)
この関数方程式を満たす関数 F(X) は、正値関数となる。すなわち、
全てのXに対して、F(X)>0
実際に、F(X)=F(X)F(1) で、F(1)=0 とすると、矛盾するので、F(1)≠0 である。
このとき、F(1)=F(1)F(1) より、F(1)=1 となる。
今、ある正数 a に対して、F( a )=0 と仮定すると、F(X)=F(a・X/a)=F(a)F(・X/a)=0
で矛盾するので、全ての実数に対して、F(X)≠0 となる。このとき、全ての実数に対して、
F(X)=F(√X)2>0 が成り立つ。
よって、log F(X)=G(X) とおくと、G(XY)=G(X)+G(Y) で、(2)の関数方程式になり、結局
Cauchy の方程式に帰着される。G(X)=Alog X より、F(X)=XA (Aは定数)となる。
(参考文献:井上正雄 著 関数方程式(東京出版)
加藤順二 著 微分方程式の解の存在(数研出版))
(追記) 平成22年10月12日付け
当HPがいつもお世話になっているHN「FN」さんが、この関数方程式について考察された。
上記において、F(x+y)=F(x)+F(y) 等の関数方程式が考えられているが、解析学分野
であるから、当然のことであるが、大体連続性を仮定している。連続性を仮定しない場合を考
えてみよう。
連続性を仮定しないとすると、例えば、関数方程式 F(x+y)=F(x)+F(y) に、F(1)=1
をつけたとしても相当多くの無茶苦茶な関数が存在すると思われる。
そこで式が2つ成り立つ場合を考える。即ち
実数 x に対して定義された実数値関数 F(x) が任意の実数 x 、y に対して、
F(x+y)=F(x)+F(y) 、F(xy)=F(x)F(y)
を満たしている。このとき、 F(x)
を求めよ。ただし、 F(x) は定数ではないとする。
F(x)=x が条件を満たすのは明らかで、これ以外にはなさそう...。
このことを証明してください。
FNさんが証明を与えられました。(平成22年10月16日付け)
有理数 x に対して、F(x)=x は容易ですが、これも含めて書きます。
F(x)=F(x+0)=F(x)+F(x) より、 F(0)=0
F(−x)+F(x)=F(−x+x)=F(0)=0 より、 F(−x)=−F(x)
F(x)=F(x・1)=F(x)・F(1) で、F(x)は恒等的に0ではないから、 F(1)=1
x≠0 のとき、 F(1/x)F(x)=F(1/x・x)=F(1)=1 より、 F(1/x)=1/F(x)
特に、F(1/x)F(x)=1 より、F(x)≠0 である。
F(x+y)=F(x)+F(y) を繰り返し使って、n が自然数のとき、 F(nx)=nF(x)
(厳密には数学的帰納法)
x=1 とおいて、F(n)=n
m、n が自然数のとき、 F(n/m)=F(n)F(1/m)=n・1/F(m)=n/m
F(−x)=−F(x) より、すべての有理数 x について、 F(x)=x
x>0 のとき、 F(x)=F((√x)2)=(F(√x))2>0 (∵ F(√x))≠0)
従って、x>y のとき、 F(x)−F(y)=F(x)+F(−y)=F(x−y)>0 より、
F(x)>F(y) が成り立つ。
あとは有理数は実数全体で稠密だからでもいいのですが。
F(x)≠x となる x があったとする。
F(x)<x とすると、 F(x)<r<x となる有理数 r がある。
r<x より、 F(r)<F(x) となり、 F(x)<r=F(r)<F(x) となり矛盾。
F(x)>x とすると、 F(x)>r>x となる有理数 r がある。
r>x より、 F(r)>F(x) となり、 F(x)>r=F(r)>F(x) となり矛盾。
以上から、すべての x について、 F(x)=x となる。
FNさんからの補足です。(平成22年10月16日付け)
2つ目の条件「任意の実数 x、y に対して、F(xy)=F(x)F(y)」をちょっと弱くして、
「任意の実数 x に対して、F(x2)=F(x)2」
に変えることができます。もう少し弱くして、
「x>0 のとき、F(x)>0」
に変えることもできます。でも、このほうが問題は簡単になります。もともとの問題は「実数
体の自己同型は恒等変換だけか」あるいは「実数体から実数体への準同型は恒等写像と
0写像(すべての x に0を対応させる)だけか」です。
実数を複素数に変えます。
複素数 x に対して定義された複素数値関数F(x)が任意の複素数 x、y に対して、
F(x+y)=F(x)+F(y) 、F(xy)=F(x)F(y)
を満たしている。このとき、F(x)を求めよ。ただし、F(x)は定数ではないとする。
F(x)=x と F(x)=(x の共役複素数) が条件を満たすのはすぐわかります。
この2つ以外になければきれいなのですが、残念ながらそうはならないそうです。これ以外
に無限に多くのF(x)があるそうです。
Zorn の補題を使って極大Filterがどうのこうのという議論をして存在が証明されるというた
ぐいのものらしいです。実数全体の像が複素平面で稠密であるというわけのわからないもの
だそうです。
実数で常識的な結果になったのは、大小関係があり、Fが大小関係を保存することから、
大小関係の保存が連続性の代わりになったということのようです。複素数では、大小関係が
なく連続性の代わりになれるものがないということかなと思います。
次は、自然数の場合を考えます。しかし同じ式2つを仮定すれば、F(n)=n
は直ちに出ま
す。そこで一方を少し弱めて、不等式にします。
自然数 n に対して定義され自然数値を取る関数 F(n) が任意の自然数 m、n
に
対して、 F(m+n)≦F(m)+F(n) 、 F(mn)=F(m)F(n) を満たしている。
このとき、 F(n) を求めよ。ただし、 F(n) は定数関数ではないとする。
F(n)=n が条件を満たすのは明らかで、これ以外にはなさそうです。
まず、F(2)=2 を仮定して、F(n)=n を示してください。
FNさんが上記の問題に証明を与えられた。(平成22年10月23日付け)
(証明) F(n)は自然数値をとる関数なので、F(1)≠0
このとき、F(1)=F(1)F(1) より、 F(1)=1
F(n)=n であることを数学的帰納法により示す。
n=1 のときは、 F(1)=1 であるので成り立つ。
n=2 のときは、 仮定より、 F(2)=2 であるので成り立つ。
n≧2 とし、n 以下では命題が成り立つものと仮定する。
n+1 が合成数 すなわち n+1=st (s、t≦n) のとき、帰納法の仮定により
F(n+1)=F(st)=F(s)F(t)=st=n+1 となり、n+1のときにも命題が成り立つ。
n+1 が素数のとき、 n+2 は偶数 すなわち 合成数なので、
n+2=st (s、t≦n+1) に対して、 F(n+2)=n+2
このとき、 n+2=F(n+2)≦F(n+1)+F(1)=F(n+1)+1 より、
F(n+1)≧n+1
一方、 F(n+1)≦F(n)+F(1)=n+1 より、 F(n+1)=n+1 なので、
n+1のときにも命題が成り立つ。
以上から、全ての自然数 n に対して、 F(n)=n が成り立つ。 (証終)
(コメント) FNさんに感謝します。 F(2)=2 の証明は難しそうですね!
F(2)=2 が成り立つことをFNさんにご教示いただきました。(平成22年10月26日付け)
(証明) F(2)≦F(1)+F(1)=2 より、 F(2)=1 または 2 である。
F(2)=1 とする。さらに、F(n)は恒等的に 1 ではないから、ある n について、
F(n)≧2 である。
F(mn)=F(m)F(n) を繰り返し使って、 F(nk)=F(n)k
F(m+n)≦F(m)+F(n) を繰り返し使って、 F(Σak)≦ΣF(ak)
(いずれも厳密には数学的帰納法で示される)
m<2p のとき、 F(m)≦p であることを示す。
m を2進法で表して、 m=Σct・2t とする。
ただし、 t は、0 から p−1 までで、ct は、0 か 1
F(2)=1 で、ct は、0 か 1 だから、F(ct・2t)=F(ct)F(2)t=F(ct) は、0 か 1
従って、 F(m)=F(Σct・2t)≦ΣF(ct・2t)≦p
n<2p となる p をとると、 nk<2kp
よって、上記より、 F(nk)≦kp
F(n)≧2 より、 F(nk)=F(n)k≧2k なので、 2k≦kp となる。
これがすべての自然数 k について成り立つことになるがそれは不可能。
以上から、 F(2)=2 でなければならない。 (証終)
(注意) 指数関数は、1次関数よりはるかに大きいから、これで十分だが具体的に書くなら、
k>2として、2k=(1+1)k>1+k+k(k−1)/2 だから、k>2p ぐらいで、
2k>kp となる。
(コメント) FNさんに感謝します。
(追記) 令和2年5月13日付け
鳥取大学 前期理系(2020)で次の問題が出題された。入試問題で加法定理や和積の
公式を堂々と証明させる時代にあって、このような出題の仕方もありかなと思う今日この頃
である。
問題 微分可能なxの関数F(x)が任意の実数x、yに対して次の関係を満たすとき、以下の
問いに答えよ。
F(−x)=−F(x) 、{F(x)}2+{F’(x)}2=1 、
F’(x+y)=F’(x)F’(y)−F(x)F(y) 、F’(0)=1
(1) F(0)を求めよ。
(2) F’(x)は偶関数であることを証明せよ。
(3) F’(u)−F’(v)=−2F((u+v)/2)F((u−v)/2)
(4) F’(x)が微分可能であることを示し、F”(x)=−F(x)を証明せよ。
(解)(1) 条件より、 F(0)=−F(0) なので、 F(0)=0
(2) F’(x−x)=F’(x)F’(−x)−F(x)F(−x) より、 1=F’(x)F’(−x)+{F(x)}2
よって、 1=F’(x)F’(−x)+1−{F’(x)}2 より、 F’(x)F’(−x)={F’(x)}2
ここで、 F’(x)=0 とすると、 {F(x)}2=1 となり、 F(0)=0 に矛盾する。
よって、 F’(x)≠0 なので、 F’(−x)=F’(x) となり、 F’(x)は偶関数である。
(別解) F(−x)=−F(x) の両辺をxで微分して、 −F’(−x)=−F’(x)
よって、 F’(−x)=F’(x) となり、 F’(x)は偶関数である。
(3) x=(u+v)/2 、y=(u−v)/2 とおくと、 x+y=u 、x−y=v
このとき、
F’(u)−F’(v)
=F’(x+y)−F’(x−y)
=F’(x)F’(y)−F(x)F(y)−(F’(x)F’(−y)−F(x)F(−y))
=F’(x)F’(y)−F(x)F(y)−F’(x)F’(y)−F(x)F(y)
=−2F(x)F(y)=−2F((u+v)/2)F((u−v)/2)
(4) F’(x+h)−F’(x)=−2F(x+h/2)F(h/2)=−2F(x+h/2)(F(h/2)−F(0))
よって、
limh→0(F’(x+h)−F’(x))/h
=−2limh→0F(x+h/2)(F(h/2)−F(0))/h
=−2F(x)・F’(0)/2
=−F(x) より、 F”(x)=−F(x)
以上から、F’(x)は微分可能で、 F”(x)=−F(x) が成り立つ。
(コメント) 条件より、 F(x)=sin x 、F’(x)=cos x を背景に問題が作られている。
特に、F’(x+y)=F’(x)F’(y)−F(x)F(y) は、cos x の加法定理で、その証
明方法を振り返ると、自然に(3)の証明は導かれると思う。
(追記) 令和5年4月29日付け
京都大学 後期文系(2004)で次の問題が出題された。関数方程式の問題っぽいが実質
は数と式の計算(数学I)である。
問題 関数F(x)は次の2条件を満たす。
(1) F(x+y)=F(x)F(y) (x、y は任意の実数)
(2) F(3)=8
このとき、F(1)=2 であることを示せ。ただし、F(x)は実数とする。
(解) 題意より、 F(3)=F(1+1+1)=F(1)3=8 すなわち、 F(1)3−23=0
よって、 (F(1)−2)(F(1)2+2F(1)+4)=0
ここで、F(1)は実数なので、 F(1)2+2F(1)+4≠0 である。
よって、 F(1)=2 である。 (終)
(コメント) ときどき京都大学の入試問題で見受けられる「見かけ倒し」の問題である。全受
験生が完答出来たことだろう。
関数方程式らしい考察をしておこう。
まず、 F(0)≠0 である。
実際に、 F(1)=F(1)F(0) で、F(0)=0 とすると、F(1)=0
このとき、 F(3)=F(1+1+1)=F(1)3=0 となり、仮定 F(3)=8 に矛盾する。
よって、 F(0)≠0 である。同様にして、 F(1)=0 とすると矛盾なので、 F(1)≠0
このとき、 F(1)=F(1)F(0) から、 F(0)=1 となる。
F(x)=F(x/2)F(x/2)=F(x/2)2≧0 で、F(1)≠0 なので、
全ての実数 x に対して、 F(x)>0 となる。
自然数 n に対して、F(1)=F(1/n)n より、 F(1/n)=F(1)1/n
自然数 m、n に対して、F(m/n)=F(1/n)m=F(1)m/n
また、 F(0)=F(x)F(−x) 、F(0)=1 より、 F(−x)=1/F(x)=F(x)-1
よって、F(−m/n)=F(1)-m/n なので、有理数 r に対して、F(r)=F(1)r が成り立つ。
ここで、F(x)の連続性を仮定すれば、全ての実数 x に対して、 F(x)=F(1)x となる。
問題の仮定から、 F(3)=F(1)3=8 なので、 F(1)=2 となる。
(コメント) F(1)の値を求めるだけだったら、「F(x)の連続性」を仮定するまでもないという
ことが分かった。
以下、工事中