
「幾衰」と書いて読み方は「きすい」でいいのだろうか?「幾」には「いくらか」という意味が
あり、「衰」には「衰える、転じて、年をとる」という意味があるので、「幾衰法」の意味合いは、
自ずと掴めることと思う。
問 題 A を頭に、5人兄弟 A 、B 、C 、D 、E がいる。5人の年齢の合計は100歳で、
B は A より 7 歳若く、C は B より 6 歳若く、D は C より 3 歳若く、E は D より
8 歳若いという。5人の年齢をそれぞれ求めよ。
この問題は、和算では幾衰法と呼ばれる方法で、次のように解かれている。
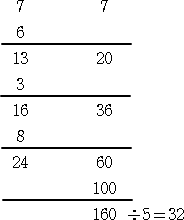
よって、 A は、32歳で以下順次、B は、25歳、C は、19歳、D は、16歳、E は、8歳、
上記の計算を補足すると、
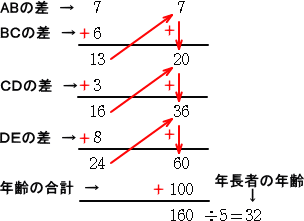
上記の計算の第1列では、B 、C 、D 、E 個々の A との年齢差を計算し、それを随時、
第2列に加えることにより、A から自分までで A の年齢にならすのに不足する分を計算し
ている。最後に、5人の年齢の合計を加えることにより、その計算結果は、A の年齢 5人
分となる。このことから、A の年齢が求められている。
(コメント) この幾衰法という手法は、年齢計算に関わらず、いろいろなところで応用でき
そうでね!
(参考文献:桐山光弘・歳森 宏 著 江戸の数学 (日刊工業新聞社))