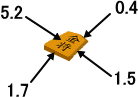将棋では、対局の前に先手後手を決めるために、「歩」を5枚取って畳みに振り、「歩」の
方が「と金」よりも多い場合は、上座の方が先手という約束がある。
また、将棋とは違うが、「まわり将棋」とか「金転がし」とか言われるゲームでは、金4枚を
振って、その出方によって駒の進む数が決まる。これなどは、誰でもどこかでやったことが
あるかもしれない。
そこでは次のようなルールになっている。(地方によって多少違うかもしれない?)
4枚の「金」の表の枚数分駒を進めるのが原則だが、特に、
(1) 4枚の「金」がすべて表 ・・・・・ 4つ進めて、もう一度振れる
(2) 4枚の「金」がすべて裏 ・・・・・ 20進める
(3) 1枚の「金」が横 ・・・・・ 5進め、さらに、残りの「金」の出方の分進める
(4) 1枚の「金」が縦 ・・・・・ 10進め、さらに、残りの「金」の出方の分進める
(5) 1枚の「金」が逆さ立ち ・・・・・ 100進め、さらに、残りの「金」の出方の分進める
(6) 駒が重なったり将棋盤から落ちたら、進めない
上記のルールを見ていると、駒の出にくさを次のように考えていると思われる。