BD、ACの交点をEとする。Eが次の条件を満たすとき、それぞれの四角形ABCDの面積Sを
求めよ。
(1) EはBDを3:4に内分する。
(2) EはBDを2:3に内分する。
(コメント) とりあえず、(1)の図を描いてみた。
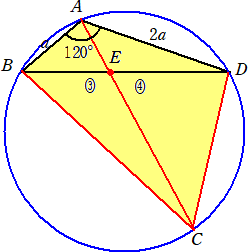 =
=余弦定理より、 BD2=a2+4a2−4a2(−1/2)=7a2 から、 BD=
正弦定理より、
このとき、 AB=(√21)/7 、DA=2(√21)/7 、BE=3
△ABD=(1/2)・2a2・sin120°=3
らすかるさんが考察されました。(令和7年10月21日付け)
多分うまい解き方があるのだろうと思いますが、全く思いつかなかったのでゴリゴリ計算し
ました。
BE : ED=a : b のとき、t=a/(a+b) とすると、AE : EC=7t^2-4t+1 : 7t(1-t)
これより、 (四角形ABCD)={(3t+1)/(7t^2-4t+1)}△ABD
ある角がθ、対辺が a、残る2辺の比が b : c である三角形の面積は、
S=(a^2sinθ)/{2(b/c+c/b-2cosθ)}
であることから、 △ABD=3√3/14
よって、四角形ABCDの面積は、(3√3)(3t+1)/{14(7t^2-4t+1)} なので、
(1) t=3/7 を代入して、6√3/7
(2) t=2/5 を代入して、165√3/182
GAI さんからのコメントです。(令和7年10月21日付け)
解答、ありがとうございます。2つとも同じ値になっていました。
自分のやり方に較べ、遥かに簡略な方法でらすかるさんは求められています。
(コメント) そうか、方べきの定理か...。らすかるさんの
BE : ED=a : b のとき、t=a/(a+b) とすると、AE : EC=7t^2-4t+1 : 7t(1-t)
を追認してみました。
AB=(√21)/7 、DA=2(√21)/7 、BD=
BE : ED=a : b のとき、 BE=(a/(a+b))
そこで、 a/(a+b)=t とおくと、 BE=t
∠ABD=θ とおくと、余弦定理から、
cosθ=(3/7+3−12/7)/(2・(√21)/7・
このとき、 AE2=3/7+3t2−2・(√21)/7・t
よって、 AE=((√21)/7)√(7t2−4t+1)
方べきの定理より、 AE・EC=3t(1−t) なので、
EC=3t(1−t)・(
したがって、
AE : EC=((√21)/7)√(7t2−4t+1):(√21)t(1−t)/√(7t2−4t+1)
=7t2−4t+1 : 7t(1−t)
#ようやく、スッキリしました。らすかるさんに感謝します。
らすかるさんから追記をいただきました。(令和7年10月21日付け)
「簡略な方法」に見えるのは、おそらく「途中計算の大半を省略」したためかと思います。
公式っぽいものを出すだけで大変手間がかかっています。
△ABCにおいて、AB : AC=b : c であるとし、∠A=θ、BC=a とする。
AB=bk、AC=ck とすると、余弦定理により、a^2=b^2k^2+c^2k^2-2bck^2cosθ
これを k について解くと、k=a/√(b^2+c^2-2bccosθ)
本問の場合は、a=√3、b=1、c=2、θ=120°なので、代入して k を求めると、
k=√3/√(1+4+2)=√(3/7)=√21/7 から、AB=bk=√21/7、AC=ck=2√21/7
また、各辺の2乗は、
a^2 、(bk)^2=a^2b^2/(b^2+c^2-2bccosθ) 、(ck)^2=a^2c^2/(b^2+c^2-2bccosθ)
簡略化のため、t^2=b^2+c^2-2bccosθ とすると、(bk)^2=a^2b^2/t^2 、(ck)^2=a^2c^2/t^2
これを、
# 各辺の長さの2乗をp,q,rとすると、三角形の面積はS=(1/4)√{2(pq+qr+rp)-(p^2+q^2+r^2)}
という変形ヘロンの公式に代入して整理すると、S=(1/4)√{2(pq+qr+rp)-(p^2+q^2+r^2)}
(途中計算省略)
=a^2/(4t^2)*√{(2b^2+2c^2-t^2)t^2-(b^2-c^2)^2}
=a^2/(4(b^2+c^2-2bccosθ))*√{(2b^2+2c^2-(b^2+c^2-2bccosθ))(b^2+c^2-2bccosθ)-(b^2-c^2)^2}
(途中計算省略)
=(a^2bcsinθ)/{2(b^2+c^2-2bccosθ)}
=(a^2sinθ)/{2(b/c+c/b-2cosθ)}
ここまでで、AB=√21/7、AC=2√21/7、S=(a^2sinθ)/{2(b/c+c/b-2cosθ)} が得られました。
次に、これを座標に当てはめます。
円を x^2+y^2=1 とし、B(-√3/2,1/2)、D(√3/2,1/2)
Bを中心として半径が√(3/7)である円:(x+√3/2)^2+(y-1/2)^2=3/7 と x^2+y^2=1 の交点
を求めると、A(-3√3/14,13/14)
Eは、t=0 のとき、Bに一致、t=1 のとき、Dに一致するように、
E=B+t(D-B)=((t-1/2)√3,1/2)
とします。
Aを通る直線の式を y=m(x+3√3/14)+13/14 とおくと、y軸に平行な直線を表せず問題があ
るので、 x=m(y-13/14)-3√3/14 とします。
これに、E((t-1/2)√3,1/2) を代入してmを求めると、m=-(7t-2)/√3
よって、直線の式は、
x=-{(7t-2)/√3}(y-13/14)-3√3/14=-(√3/42){9+(7t-2)(14y-13)}
これを、x^2+y^2=1 に代入してxを消去し、yの式を導出すると、
(1/588){9+(7t-2)(14y-13)}^2+y^2=1
(途中計算省略)
28(7t^2-4t+1)y^2-4(7t-2)(13t-5)y+13(13t^2-10t+1)=0
より、 y=13/14 、(13t^2-10t+1)/{2(7t^2-4t+1)}
AEのy座標の差は、13/14-1/2=3/7
ECのy座標の差は、1/2-(13t^2-10t+1)/{2(7t^2-4t+1)}=3t(1-t)/(7t^2-4t+1)
よって、AE:EC=3/7:3t(1-t)/(7t^2-4t+1)=(7t^2-4t+1):7t(1-t) なので、
AE:AC=(7t^2-4t+1):(7t^2-4t+1)+7t(1-t)=7t^2-4t+1:3t+1
となり、 (四角形ABCD)={(3t+1)/(7t^2-4t+1)}△ABC が言えました。
DD++ さんからのコメントです。(令和7年10月23日付け)
これ、そんなにややこしいですかね?
円に内接する四角形ABCDとその対角線の交点Eについて、
AB*AD/AE = BC*BA/BE = CD*CB/CE = DA*DC/DE
が成り立ちます。(証明は三角形の相似で一瞬)
BC*BA/BE = DA*DC/DE
の部分を使います。
事前に、正弦定理で、BD =
(1) AB = x とすると、AD = 2x で、CB = 3y とすると、CD = 2y
△ABDと△CBDに注目して、余弦定理より、7x^2 = 7y^2 = 3
よって、求める面積は、S = (x^2 + 3y^2) *
(2) AB = x とすると、AD = 2x で、CB = 4y とすると、CD = 3y
△ABDと△CBDに注目して、余弦定理より、7x^2 = 13y^2 = 3
よって、求める面積は、S = (x^2 + 6y^2) *
らすかるさんからのコメントです。(令和7年10月24日付け)
やはり簡単な解き方があったのですね。全く思いつきませんでした。
(コメント) DD++ さんの解法は、素晴らしい切れ味ですね!感動しました。
(AB*AD/AE = BC*BA/BE の証明)
△EAD∽△EBC より、AD : AE=BC : BE から明らか。
他も同様。
GAI さんからのコメントです。(令和7年10月31日付け)
円に内接する四角形ABCDとその対角線の交点Eについて、
AB*AD/AE = BC*BA/BE = CD*CB/CE = DA*DC/DE
が成り立ちます。(証明は三角形の相似で一瞬)
が面白く、この値が一体どんな値を取るのかを
(1) EはBDを3:4に内分する。
(2) EはBDを2:3に内分する。
の場合について調べると、(1)なら、
そこで、この円に内接する四角形での設定を一般化して、半径Rの円に内接する四角形
ABCDで、
AD=k*AB 、∠BAD=θ
対角線AC、BDの交点をEとするとき、
BE : ED=1 : t
である時の
AB*AD/AE = BC*BA/BE = CD*CB/CE = DA*DC/DE
はどんな値を取るのかを求めることをしてみた。その結果、
2*k*(t+1)*R*sin(θ)/√(k^2+t^2+2*k*t*cos(θ))*(k^2-2*k*cos(θ)+1))
が上記の各比が一定の値となるものとなるようだ。
円に内接する四角形にトレミーの定理や、DD++氏が指摘した4つの各組での比の相等な
ど、ある意味美しい関係にバランスが保たれている姿が見れました。
